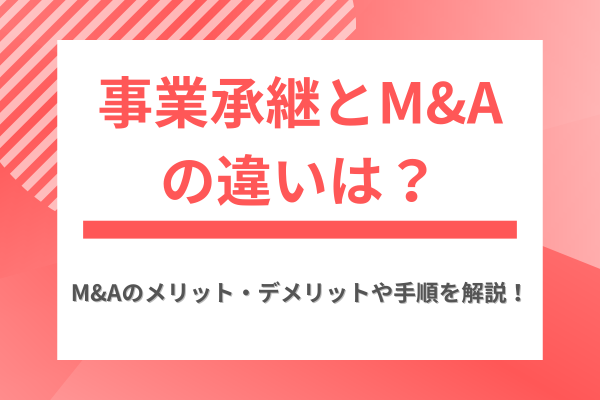「M&Aによる事業承継とは何か?」
「事業承継でM&Aを選ぶメリットは?」
M&Aによる事業承継とは、会社の経営権を第三者の企業に譲渡することで事業を継続させる手法です。
親族や従業員に適切な後継者がいない場合の有効な選択肢となっています。
近年、後継者不足により廃業を検討する中小企業が増加している中、M&Aは後継者不在問題の解決、従業員雇用の維持、経営者の株式譲渡益獲得といったメリットがあります。
一方で、条件面での交渉難航や成立まで長期間を要するデメリットも存在します。
今回は、「M&Aによる事業承継の具体的な流れ」や「成功させるためのポイント」などについて詳しく解説していきます。
事業承継を検討されている経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
監修者

代表理事
小野 俊法
経歴
慶應義塾大学 経済学部 卒業
一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。
その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。
その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。
投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。
事業承継とは?
事業承継とは、会社の経営を現在の経営者から後継者へと引き継ぐことです。
引き継がれるものは経営権、経営資源、物的資産の3つの要素に分かれており、これらを適切に後継者へバトンタッチする必要があります。
事業承継の方法は後継者によって3つに分類されます。
親族内事業承継では息子や娘に引き継ぎ、社内事業承継では従業員や役員に承継します。M&Aによる事業承継では他社への売却や合併を行います。
事業承継は単なる会社の引き渡しではありません。経営者の思いと共に、会社の未来を託す重要なプロセスなのです。
M&Aとは?
M&Aとは会社の合併や買収をあらわします。ビジネスの世界でよく聞く言葉ですが、会社や事業がひとつにまとまったり、他の会社の経営権を持つことなどが含まれます。
新しいサービスの展開や人手不足の解消、後継者問題への対応のためなど、企業ごとの事情に合わせて会社の強みや弱みを補うために実施されます。
たとえば、飲食店を長年続けていた経営者が高齢となり、家族が後を継がなかった場合、事業を他社に売却して店舗やノウハウを引き継ぐケースがあります。
その結果、会社やブランドが次世代へと受け継がれ、雇用やサービスの継続も期待できます。
M&Aの種類
M&Aの主な種類は、以下の通りです。
| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 株式を売買して経営権を移転 | 手続きが簡単、スピーディー |
| 事業譲渡 | 事業の一部または全部を売買 | 柔軟な選択が可能 |
| 合併 | 複数企業が統合して一つに | 規模拡大効果が高い |
日本で最も多く使われているのは株式譲渡という買収手法で、中小企業のM&Aの8~9割を占めています。
株式譲渡は手続きが簡単で、スピーディーな買収が可能です。
一方、事業譲渡は特定の事業だけを売買するため、不要な資産や負債を引き継がなくて済むメリットがあります。
事業承継とM&Aの違い
事業承継は会社の経営を後継者に引き継ぐ手続き全体を指します。
一方でM&Aは事業承継の選択肢の一つであり、第三者への譲渡手段にあたります。
つまり、事業承継という大きな枠組みの中にM&Aが含まれているのです。
| 項目 | 事業承継 | M&A |
|---|---|---|
| 意味 | 経営権を後継者に引き継ぐ手続き全体 | 企業や事業の経営権を第三者へ譲渡 |
| 対象範囲 | 親族内・社内・外部すべて | 外部の第三者のみ |
| 主な目的 | 会社の継続と発展 | 後継者不在の解決 |
| 実施方法 | 相続・贈与・株式譲渡など | 株式譲渡・事業譲渡など |
| メリット | 経営方針の継続性 | 適任者を幅広く探せる |
社長が息子に会社を託すなら親族内承継、従業員に任せるなら社内承継になります。
しかし適任者がいない時、外部企業への売却を選ぶとM&Aによる事業承継となります。
近年は後継者不足により、M&Aを活用する経営者が増えています。
M&Aによる事業承継の3つのメリット

以下では、M&Aによる事業承継を検討されている方のために、M&Aを活用することで得られる3つのメリットについてご紹介します。
- 後継者不在問題を解決できる
- 従業員の雇用を維持できる
- 経営者や株主は株式譲渡益等の利益を得られる
後継者不在問題を解決できる
親族や従業員の中に適切な後継者が見つからない場合でも、M&Aなら幅広い経営経験者を後継者として選ぶことができます。
血縁関係に関係なく、資質やモチベーションに優れた人物を後継者に選べるメリットがあります。
また、従業員の雇用維持や取引先との関係継続も可能で、廃業による社会的影響を回避できます。
さらに、株式売却により創業者利益を現金で受け取れるため、老後資金の確保にもつながります。
従業員の雇用を維持できる
廃業を選択した場合、従業員は職を失い新しい仕事を探す必要が生じます。
しかし、M&Aでは事業が継続されるため、基本的に従業員の雇用も継続されます。
株式譲渡の場合は雇用契約に変更はなく、事業譲渡でも新たに契約を結び直す際、基本的に同条件で雇用が継続される仕組みになっています。
経営者や株主は株式譲渡益等の利益を得られる
M&Aでの株式譲渡により、経営者や株主は大きな譲渡益を獲得できます。
事業承継における株式譲渡では、経営者が保有する株式を売却することで現金を手に入れることができます。
株式譲渡による売却益には、個人の場合20.315%の譲渡所得税が課税されますが、事業譲渡の法人税約30%と比較して税負担を抑えられる点が魅力です。
M&Aによる事業承継の3つのデメリット
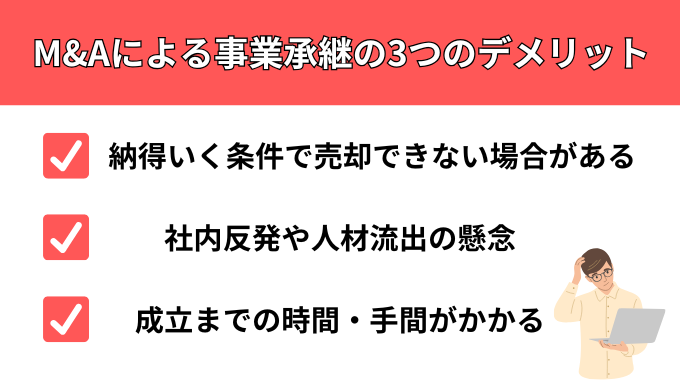
M&Aによる事業承継にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
- 納得いく条件で売却できない場合がある
- 社内反発や人材流出の懸念
- 成立までの時間・手間がかかる
以下では、代表的なデメリット3つについて解説します。
納得いく条件で売却できない場合がある
買い手と売り手の双方が合意しなければ取引は成立しないため、売り手側の希望だけでは条件を決められません。
売却価格は相場観や経営者の希望額を基準に交渉が始まりますが、買い手が交渉テーブルに着かない場合もあります。
また、買収監査の過程で想定外の簿外債務などが見つかると、価格引き下げを要求される場合があります。
長期間をかけて相手を探した結果、よい相手が見つからなかった事例も決して少なくありません。
社内反発や人材流出の懸念
M&Aが実施されると、従業員は新しい経営体制や企業文化に直面することになります。
経営者の変更により、これまでの人間関係や働き方が大きく変わるため、従業員は不安やストレスを感じやすくなります。
また、労働条件や人事制度の統合により、待遇が悪化したり職場環境が変化したりすると、従業員の反発を招きやすくなります。
さらに、買収する側と売却される側の従業員が同じ職場で働くようになると、価値観や意見の違いから摩擦が生じることがあります。
成立までの時間・手間がかかる
M&Aによる事業承継で最も悩む点は、成立までに多くの時間や手間がかかることです。
| 工程 | 主な作業内容 | 標準的な期間 | 遅延要因 |
|---|---|---|---|
| マッチング | ・買い手候補の探索 ・初期的な条件すり合わせ ・秘密保持契約の締結 | 1~3ヶ月 | ・適切な買い手が見つからない ・業界や規模の条件が合わない |
| 条件交渉 | ・売却価格の決定 ・従業員の処遇協議 ・経営権移譲の条件設定 | 2~4ヶ月 | ・価格での意見対立 ・雇用条件での難航 ・経営方針の相違 |
| 企業調査 (デューデリジェンス) | ・財務状況の詳細確認 ・法的リスクの調査 ・事業内容の精査 | 1~2ヶ月 | ・書類準備の遅れ ・隠れた問題の発見 ・追加調査の必要性 |
| 契約書作成・締結 | ・最終契約書の作成 ・法的手続きの完了 ・関係者への報告 | 1ヶ月 | ・契約条件の最終調整 ・法的承認手続きの遅延 |
| 統合作業 | ・経営体制の移行 ・システム統合 ・従業員への説明 | 3~6ヶ月 | ・組織文化の違い ・システム統合の複雑さ |
- 順調な場合: 6ヶ月~1年
- 交渉が難航する場合: 1~2年
- 複雑なケース: 2年以上
特に買い手がすぐに見つからなかったり、交渉が難航したりした場合、半年から一年以上かかることがあります。
場合によっては数年単位で時間が必要になるケースもあるので早めの準備が大切です。
M&Aによる事業承継の流れ
M&Aによる事業承継は、以下の手順で進めることができます。
まずは自社の財務状況や経営課題を「見える化」します。
会社の資産状況、株式保有状況、株式評価額を確認し、M&A以外の選択肢も含めて検討することが重要です。
譲渡価格を高めるために、経営改善や「磨き上げ」を実施します。
財務体質の改善や業務効率化を通じて、買い手にとって魅力的な会社にしていきます。
専門知識が必要なため、M&A仲介会社やアドバイザーに依頼するのが安全です。
バリュエーション(企業価値評価)も専門家に任せることで、適正な価格設定ができます。
仲介会社がロングリストを作成し、そこから数社に絞り込んだショートリストを作ります。
「ノンネームシート」という匿名の企業概要書で、候補企業に打診を行います。
興味を示した候補企業と秘密保持契約を締結し、詳細な情報を開示します。
お互いの調査を通じて、相性や条件面を確認していきます。
トップ面談を経て、M&Aスキームや譲渡価格などの主要条件をまとめた基本合意書を締結します。
買い手企業が財務・法務の詳細調査を行います。
売り手側は正確な情報を提供し、調査に協力することが求められます。
最終条件を確定し、最終契約書を締結します。
株式の引き渡しが完了すると、M&Aによる事業承継が完了となります。
このように段階的に進めることで、M&Aによる事業承継を成功させることができます。
専門家のサポートを受けながら、計画的に取り組むことが重要です。
M&Aによる事業承継を成功させるポイント
ここでは、M&Aによる事業承継を成功させるポイントをご紹介します。
M&Aによる事業承継の成功に向けて、下記ポイントを押さえておきましょう。
- 事前準備を徹底する
- シナジー効果を発揮できる買い手を見つける
- 自社の強み・課題と経営状況を正確に把握する
事前準備を徹底する
M&Aで事業承継を成功させるには、事前準備を徹底することが最も重要なポイントです。
事業承継は複雑な手続きが多く、思い立ってすぐに実施できるものではありません。
10年など長期目線での計画的な準備が成功のポイントとなります。
事前に準備すること
| 準備項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社の現状把握 | 資産・負債・株式評価額の確認 |
| 経営状況の見える化 | 業界将来性・従業員状況・株主構成 |
| 企業価値評価 | 専門家による客観的な価値算定 |
| 資料整理 | デューデリジェンス対応準備 |
| 後継者選定 | 適任者の確認と育成計画 |
| 税金対策 | 相続税・贈与税の事前シミュレーション |
準備には時間がかかるため、経営者が60歳になる前に開始することが望ましいとされています。
シナジー効果を発揮できる買い手を見つける
シナジー効果を生み出せる相手であれば、より良い条件での譲渡が実現できます。
買い手企業の多くは経営戦略としてM&Aを実施するため、シナジー効果を得られる会社を積極的に探しています。
売り手側が相乗効果を明確に示すことができれば、買い手にとって魅力的な投資対象となり、売却価格の向上や条件面での優遇につながります。
シナジー効果を発揮できる買い手を見つけるには、自社の価値を正確に把握し、買い手に分かりやすく伝える準備が欠かせません。
自社の強み・課題と経営状況を正確に把握する
M&Aによる事業承継を成功させるには、自社の強みと課題、経営状況を正確に把握することが重要です。
事業承継では買い手企業が売り手企業の価値を慎重に評価するためです。
自社の強みや弱み、事業ポートフォリオ、市場における競争優位性を分析しなければ、適切な企業価値を示せません。
また、財務諸表の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の分析により財務の健全性を確認する必要があります。
まず自社株式の評価額について相続税評価額やM&A時の企業価値を踏まえて概算を把握しましょう。
自社の現状を正確に把握することで、買い手企業との交渉を有利に進められます。
M&Aによる事業承継に関するよくある質問
M&Aによる事業承継に関するよくある質問をご紹介します
- 事業承継でM&Aを行う際に注意すべきことは何ですか?
- 事業承継M&Aに活用できる補助金にはどんなものがありますか?
- M&Aによる事業承継で起こりやすいトラブルにはどのようなものがありますか?
事業承継でM&Aを行う際に注意すべきことは何ですか?
事業承継でM&Aを行う際は、情報漏えい対策、デューデリジェンスの徹底、専門家選び、統合後の従業員ケアに注意が必要です。
M&Aを行う際に注意すべきこと
| 注意点 | 内容 | 対策方法 |
|---|---|---|
| 情報漏えい対策 | 従業員や取引先への情報流出を防ぐ | 限られた関係者のみに情報共有 |
| 株主の理解獲得 | 株主の反対でM&Aが不成立になるリスク | 事前に株主への説明と同意を取得 |
| デューデリジェンス | 買収監査が不十分だと隠れた債務が発覚 | 専門家による徹底的な調査実施 |
| 専門家選び | 信頼できるM&A仲介業者への依頼 | 実績と専門知識を持つ業者を選定 |
| 売却タイミング | 最適な売却時期を逃すリスク | 市場状況と企業価値を適切に判断 |
| 従業員のケア | 買い手側の経営方針変更による離職 | 雇用確保と待遇面の事前調整 |
情報が従業員に漏れると従業員離れや交渉失敗を招き、デューデリジェンスが不十分だと簿外債務や粉飾が発覚して経営悪化する恐れがあります。
また、契約後の統合作業を怠ると従業員への悪影響が生じます。
M&Aを成功させるには、事前の綿密な準備と専門家への相談が必要不可欠といえるでしょう。
事業承継M&Aに活用できる補助金にはどんなものがありますか?
事業承継M&Aに活用できる補助金は、以下です。
| 支援枠 | 対象者 | 補助上限額 | 補助率 | 主な対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 5年以内に親族内承継又は従業員承継を予定している者 | 800~1,000万円 | 1/2・2/3 | 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費等 |
| 専門家活用枠 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受ける者 | 買い手:600~2,000万円 売り手:600~800万円 | 買い手:1/3・1/2・2/3 売り手:1/2・2/3 | M&A支援業者手数料、デューデリジェンス費用等 |
| PMI推進枠 | M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等 | 専門家活用:150万円 事業統合投資:800~1,000万円 | 専門家活用:1/2 事業統合投資:1/2・2/3 | PMI専門家費用、設備投資等 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う者 | 150万円 | 1/2・2/3 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費等 |
事業承継M&Aを検討している経営者の方は、事業内容に応じて4つの支援枠から選択し、最大2,000万円の補助を活用することで、承継に伴う費用負担を大幅に軽減できます。
申請には公募期間があるため、中小企業庁の最新情報を確認して早めの準備をおすすめします。
M&Aによる事業承継で起こりやすいトラブルにはどのようなものがありますか?
M&Aによる事業承継では、契約内容の不備、買い手による資金流出、従業員の反発など、さまざまなトラブルが発生しやすいです。
M&Aによる事業承継で起こりやすいトラブル
| トラブルの種類 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 契約内容の不備・記載漏れ | 重要な事項が契約に規定されていない | 実行後の責任の所在が不明確になる |
| 買い手による資金流出 | 子会社の資金を買い手が吸い上げる | 従業員給与の未払い、事業停止 |
| 従業員の反発・大量退職 | 経営方針の変更に対する従業員の不満 | 事業継続の困難、ノウハウの流出 |
| 取引先との関係悪化 | 新経営者への信頼不足 | 契約打ち切り、売上減少 |
| 表明保証の違反 | 売り手が提供した情報の不正確性 | 損害賠償請求、信頼関係の破綻 |
ある会社では、M&A後に買い手企業が資金を吸い上げた結果、従業員への給与支払いが滞り、最終的に事業が停止しました。
また、親族間での後継者争いにより会社が分裂し、主要取引先が契約を見直すケースも報告されています。
M&Aによる事業承継を検討する際は、信頼できる専門家への相談と十分な買い手企業の調査が不可欠です。
まとめ
今回紹介したM&Aによる事業承継のメリット・デメリット、具体的な流れ、成功のポイントを参考に、早めの準備と計画的な取り組みを開始しましょう。
特に経営者が60歳になる前からの10年スパンでの長期準備が成功のポイントとなります。
事業承継は会社の未来を左右する重要な決断です。
一人で抱え込まず、信頼できるM&A仲介会社や専門家と連携し、従業員や取引先、そして経営者自身にとって最良の選択となるよう、自信を持って取り組んでください。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
M&Aによる事業承継は、後継者不在問題の解決や従業員の雇用維持といったメリットがある一方で、適切な買い手の選定や統合プロセスには専門的な知識と経験が不可欠です。
一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、こうした事業承継の課題を抱える企業オーナー様を総合的にサポートするために設立されました。
M&Aによる事業承継では、シナジー効果を発揮できる買い手の選定や自社の強み・課題の正確な把握が成功の鍵となりますが、JPCAはプロ経営者の輩出とマッチングを通じて、最適な後継者選定を実現します。
JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる支援体制を整えており、事前準備の徹底から統合後のフォローアップまで、事業承継に必要なすべてのプロセスをワンストップでサポートいたします。
事業承継や後継者問題でお悩みの経営者様は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。