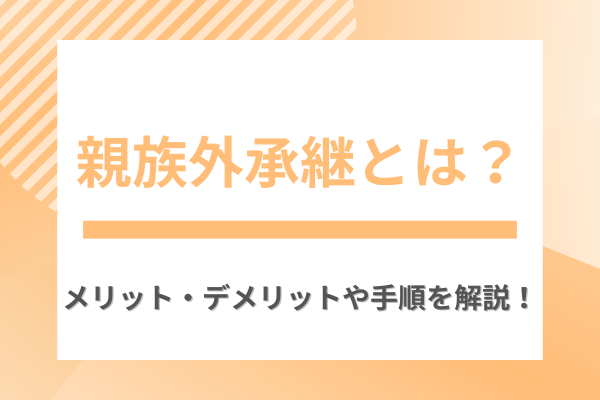「親族外承継って何?」
「親族外承継を成功させるポイントは?」
親族外承継とは、血縁関係がない役員や従業員、外部の人材などに会社や事業を引き継ぐ方法です。
近年、日本企業の事業承継において親族外承継が選ばれる割合は約6割に達しており、「脱ファミリー化」が進んでいます。
- 計画的に後継者を育成する
- 十分な引継ぎ期間を設ける
- 専門家の活用とアドバイスを受ける
今回は、「親族外承継のメリット・デメリット」や「成功させるためのポイント」などについて詳しく解説していきます。
事業承継を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
監修者

代表理事
小野 俊法
経歴
慶應義塾大学 経済学部 卒業
一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。
その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。
その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。
投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。
親族外承継とは
親族外承継は、血縁関係がない役員や従業員、外部スタッフなどに会社や事業を引き継ぐ方法です。
身内に引き継げる人がいないケースや、会社の将来をしっかり守るために、実績や信頼がある従業員や外部の適任者などを後継者として選ぶことができます。
親族内に後継者がいない問題や事業継続の観点から、注目されています。
具体的には、会社で長く働いたベテラン従業員を新しい経営者として迎えたり、外部から新しいノウハウを持つ人材を社長にするパターンなどが多いです。
社内アンケートで選ばれた従業員が社長となり、安定した成長を続けている例も有名です。
親族外承継は、柔軟に後継者を選ぶことができるので、不安を感じる方も前向きに検討する価値があります。
親族外承継の方法
親族以外に会社を承継する際の、「経営のみ承継」と「株式ごと承継」の2つのパターンについて、分かりやすくご紹介します。
経営のみ承継
経営のみ承継とは、会社の株式や資産を引き継がずに、「経営者」という役割や経営の方針だけを新しい人材に渡すことです。
親族外へ承継する場合は、社内の信頼できる従業員や、社外から責任者を招いて経営権を譲るケースが当てはまります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 経営だけを親族外の人材へ引き継ぐ。株式は現オーナーが保有したまま実施 |
| 主な方法 | 内部昇格(社内の役員や従業員に引き継ぐ)・外部招聘(外部の専門家や取引先から経営者を招く) |
| メリット | 会社文化の維持、円滑な引き継ぎ、新しい視点の導入が期待できる |
| デメリット | 新経営者の経験不足や、社内外の信頼関係の構築に時間がかかることもある |
親族外に経営を引き継ぐと、会社独自のルールやノウハウを守りながら、新しい風を取り入れやすいです。
社内の信頼できる従業員や社外から迎えた人材が経営に関わることで、社風や業務への理解と成長意欲が両立できるためです。
熟練した従業員が社長に昇格した事例や、同業他社から人材を招いて経営改革が進んだケースがあります。
株式を残したまま経営だけを渡すため、オーナー自身も安心して会社の未来を見守れます。
株式ごと承継
株式ごと承継とは、経営権に加えて自社の株式や事業用資産ごと新しい経営者へ引き継ぐやり方です。
親族以外に経営をまかせることを考えている方に向いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 会社経営と一緒に、オーナーが持っていた株式も引き継ぐ方法 |
| 主な方法 | M&A、事業譲渡、従業員や経営者への株式売却など |
| メリット | 後継者が経営権を明確に持ちやすく、意思決定が円滑にできる |
| デメリット | 売却後の資金調達や税金負担、会社運営方針変更リスク |
事業経営を親族外に引き継ぐ相談が増えており、株式も一緒に渡す方法が理解しやすいです。
次のリーダーが会社に対する発言権や責任を明確に持つことで経営が一段と安定しやすくなるためです。
たとえばM&Aを通して新しい社長が株式も取得した事例では、出資者と経営者が同じ考えで迅速に判断を行い、事業拡大に成功しています。
会社の将来を考えて一括して任せられるのは、経営も株式も両方譲る方式だから安心できます。
親族外承継のメリット

親族外承継のメリットは、以下の通りです。
- 後継者の選択肢が広がる
- 経営能力や意欲を重視して後継者が決められる
- 従業員の雇用や取引先との信頼関係が維持しやすい
親族外承継の主なメリットについて解説していきます。
後継者の選択肢が広がる
親族外承継では、後継者候補の選択肢が大幅に広がります。
親族内承継では、子どもや親族という限られた範囲から後継者を選ばなければなりません。
しかし、親族外承継なら、社内の役員や従業員はもちろん、社外の優秀な人材も候補になります。
血縁関係にとらわれず、経営能力や資質を客観的に判断して選べるメリットがあります。
経営能力や意欲を重視して後継者が決められる
親族外承継では、身内だけに限定されず、社内外から才能ややる気を重視した人選が可能です。
企業の成長には、専門知識や実績だけでなく、前向きな意欲を持った人物が重要です。
実際、従業員や外部経営者へ引継ぐケースでは、社内のモチベーションも高まりやすいと言われています。
業績向上や新しい風を社内に取り込める点も評価されています。
長年会社に貢献してきた従業員がリーダーになる場合、現場の経験を活かしながら、着実に経営を進める様子を周囲が信頼しやすくなります。
従業員の雇用や取引先との信頼関係が維持しやすい
親族外承継により、既存の人間関係を活かしながら従業員の雇用を守り、取引先との信頼関係を継続できます。
長年勤務してきた従業員や役員が後継者となる場合、社内からの理解が得られやすく、取引先に対しても以前から面識があるため信頼を築きやすいのです。
また、後継者が会社の業務や文化に精通しているため、円滑な引継ぎが可能となり、現在の経営方針や社風を維持しやすくなります。
M&Aの場合でも、8割以上のケースで従業員の雇用が完全に維持されています。
親族外承継のデメリット
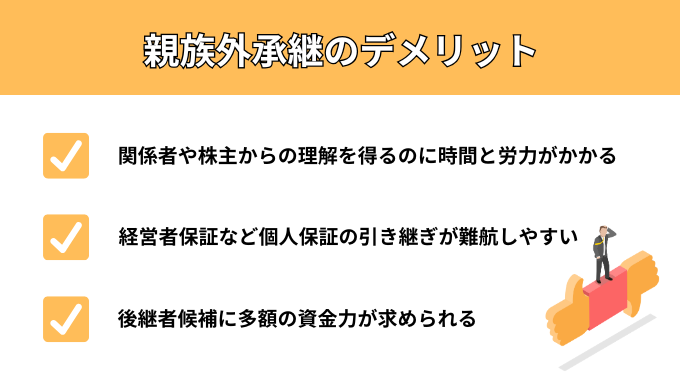
親族外承継には注意すべきデメリットも存在します。
- 関係者や株主からの理解を得るのに時間と労力がかかる
- 経営者保証など個人保証の引き継ぎが難航しやすい
- 後継者候補に多額の資金力が求められる
以下では、代表的なデメリット3つとその詳細について解説します。
関係者や株主からの理解を得るのに時間と労力がかかる
親族外承継では、関係者や株主から理解を得るために多大な時間と労力が必要になります。
株主からの理解を得られない場合、良好な関係が築けず、経営をスムーズに行えない可能性が高くなります。
現経営者の経営理念や方針に理解を示していても、後継者候補が異なる経営理念や方針を打ち出した場合は理解を示してくれないことがあります。
さらに、従業員や取引先に対しても、後継者の人物像や今後の経営方針を早い段階で説明し、不安を払拭する必要があります。
経営者保証など個人保証の引き継ぎが難航しやすい
親族外承継では、経営者保証の引き継ぎが障害となり、事業承継が思うように進まないケースがあります。
後継者候補が多額の保証債務を負うリスクを嫌がり、承継を拒否するケースが頻発しています。
また、金融機関側も、信用力や資産力に不安がある後継者への保証人変更を認めたがらないため、交渉が長期化します。
さらに、親族内承継と違い、親族外承継では後継者が会社の債務を個人で背負う動機が薄いことも、問題を複雑化させています。
後継者候補に多額の資金力が求められる
親族外承継では、後継者が株式を買い取って事業承継を完了させることが基本となります。
しかし、役員や従業員は個人資産が少ない場合が多く、会社の経営権を得るために必要な過半数以上の株式を取得するには相当な資金力が求められます。
また、事業用資産の購入や個人保証の引継ぎなど、さまざまな資金負担が発生するため、後継者には多額の資金を用意できる経済力が必要です。
株価が高い会社ほど買い取りのハードルが上がり、贈与や事業承継税制の利用、融資制度などを活用しないと資金不足に陥る可能性が高くなります。
親族外承継を行う手順
親族外承継は、6つのステップで進めることができます。計画的に取り組むことで、スムーズな事業の引き継ぎが実現できます。
会社の財務状況や課題を詳しく調べます。事業の強みと弱みを明確にして、承継前に必要な改善を行います。
社内の役員や従業員、または外部の人材から適切な後継者を選びます。経営能力や会社への理解度を慎重に評価します。
後継者と一緒に、中長期的な事業計画を作成します。資産の移転計画も含めて、具体的なスケジュールを決めます。
親族、従業員、取引先、金融機関に計画を説明します。早めの根回しで、関係者の協力を得やすくなります。
株式の譲渡価格や雇用条件について後継者と交渉し、株式譲渡契約を結びます。
株式譲渡を実行し、株主名簿を書き換えます。代表取締役を交代して、経営の引き継ぎを完了します。
親族外承継では、親族以外の人に事業を託すため、関係者の理解と協力が不可欠です。
親族外承継は計画から実行まで5~10年程度かかります。
各ステップを丁寧に進めることで、安心して事業を次世代に託すことができるでしょう。
親族外承継を成功させるための3つポイント
親族外承継を成功させるための3つのポイントをご紹介します。
- 計画的に後継者を育成する
- 十分な引継ぎ期間を設ける
- 専門家の活用とアドバイスを受ける
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
計画的に後継者を育成する
親族外承継を成功させるためには、計画的な後継者育成が欠かせません。
なぜなら、親族外承継では候補者の選定から育成まで多くの時間がかかるからです。
経営に必要な知識や業務スキルを段階的に習得させるためには、できる限り早期に承継計画を立て、教育・育成の体制を整えておくことが求められます。
| 育成段階 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 候補者選定 | 信頼できる人材の見極めと意思確認 | 1~3年 |
| 基礎育成 | 経営知識・業務スキルの習得 | 2~3年 |
| 実践経験 | 各部門での実務経験と取引先紹介 | 3~5年 |
| 経営参画 | 部分的な経営業務への参加 | 1~2年 |
実際に、後継者育成では技術・ノウハウの教育や取引先への紹介、経営に関する教育などを実施します。
営業や経理など複数の業務に携わらせる機会を設けることで、将来的に事業を安定的に運営していける人材に仕上げることができます。
十分な引継ぎ期間を設ける
親族外承継を成功させるためには、十分な引継ぎ期間を設けることが重要です。
後継者を決めてから事業承継が完了するまでの移行期間は、3年以上を要する割合が半数を上回り、10年以上を要する割合も少なくありません。
親族外承継には、後継者の育成やM&Aの相手探しなど、時間がかかる要素が多く含まれているためです。
円滑な事業承継を実現するためにも、できるだけ早く事業承継の計画を立て、準備に着手することが重要です。
専門家の活用とアドバイスを受ける
親族外承継は法律や税務の専門知識が必要な複雑なプロセスであり、一人で進めることは困難です。
専門家に相談することで、自社の現状を正確に把握し、最適な承継方法を見つけることができます。
また、関係者への説明や後継者の育成についても、経験豊富な専門家からの的確なアドバイスが得られます。
| 専門家の種類 | 主な支援内容 | 相談するメリット |
|---|---|---|
| 税理士 | 税務手続き・事業承継税制の活用 | 税負担の軽減と適切な手続き |
| 弁護士 | 法的手続き・契約書作成 | 法的リスクの回避 |
| 経営コンサルタント | 後継者選定・育成計画 | 最適な承継戦略の策定 |
| M&A仲介会社 | 買収候補先の紹介 | 幅広いネットワークの活用 |
早めに相談することで、計画的な承継が可能になり、安心して事業を引き継ぐことができるでしょう。
親族外承継に関するよくある質問
親族外承継を考えている方からは、以下のようなご質問をよくいただきます。
実際に事業承継を検討している企業や経営者の皆さまにも参考になる内容となっておりますので、記事の最後にぜひご覧ください。
- 日本企業で親族外承継が選ばれる割合はどれくらいですか?
- 親族外承継の場合、株価(自社株式の評価)はどのように決まりますか?
- 後継者をどのように選定すればよいですか?
日本企業で親族外承継が選ばれる割合はどれくらいですか?
現在、日本企業の事業承継において親族外承継が選ばれる割合は、全体の約6割に達しています。
2024年の調査では、内部昇格による承継が36.4%、M&Aなどによる承継が20.5%、外部招聘が7.5%となっており、これらを合計すると64.4%にもなります。
帝国データバンクの調査によると、2024年の事業承継では内部昇格が36.4%となり、同族承継の32.2%を上回りました。また、後継者候補の属性では「非同族」が39.3%を占め、3年連続でトップとなっています。
日本企業の事業承継は「脱ファミリー化」が進んでおり、親族外承継の割合は今後も増加していくと予想されます。
参考:全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]
親族外承継の場合、株価(自社株式の評価)はどのように決まりますか?
親族外承継(M&Aなど)の場合、株価(企業価値)は当事者間の交渉で決まりますが、評価の基礎として時価純資産法、類似会社比較法、DCF法がよく用いられます。
| 法名 | 概要・計算方法 | 主な適用ケース・特徴 |
|---|---|---|
| 時価純資産法 (コストアプローチ) | 貸借対照表の資産および負債を時価で再評価し、「資産の時価−負債の時価」で算出。 | 中小企業や業績が安定しない企業 将来予測が困難な場合に有効 成長性は織り込みにくい |
| 類似会社比較法 (マルチプル法、マーケットアプローチ) | 類似上場企業の企業価値倍率(EV/EBITDA)、株価収益率(PER)、株価純資産倍率(PBR)を使い、自社の利益や純資産に適用し評価。 | 同業の上場企業のデータがある場合 一定の客観性がある 市況影響を受けやすい |
| DCF法 (インカムアプローチ) | 将来生み出すと予想されるキャッシュ・フローを加重平均資本コストで割引き、現在価値を算出。 | 上場企業や成長企業向き 事業計画や将来予測が重要 専門性高く説明責任も果たせる |
- 時価純資産法は、中小企業や業績が安定しない企業で多用され、直近B/S資産負債の実態把握に役立ちます。
- 類似会社比較法(マルチプル法)は、類似上場企業の倍率を利用し、客観性が高い評価が可能です。
- DCF法は、将来キャッシュ・フロー予測が重視され、上場企業や高成長企業で合理的とされます。
上記は、税務評価(類似業種比準価額方式など)とは異なり、M&Aの適正価格算定に適します。
中小企業では時価純資産法+年倍法が、規模の大きいケースではDCF法が重視されます。
後継者をどのように選定すればよいですか?
親族外承継では、経営理念への理解と実務経験を重視し、段階的に後継者を選定することが重要です。
親族外承継において後継者選定が困難な理由は、親族内承継と異なり、能力や意欲を客観的に評価する必要があるためです。
後継者選定のポイント
| 選定項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 経営理念への理解 | 会社の価値観や方針への共感度 |
| 実務経験 | 業務知識と経営スキルの習得状況 |
| リーダーシップ | 周囲を巻き込む指導力 |
| コミュニケーション能力 | 社内外との円滑な関係構築力 |
| 学習意欲 | 変化への対応力と成長意識 |
| 覚悟と責任感 | 経営者としての使命感 |
社内の役員や従業員から選定する場合、既に業務に精通しているため引き継ぎがスムーズに進みます。
外部から選定する場合は、新しい視点や専門知識を期待できます。
どちらの場合も、会社の将来像と後継者の価値観が一致しているかを確認することが大切です。
まとめ
親族外承継は、血縁関係のない役員や従業員、外部の専門家などに会社や事業を引き継ぐ方法です。
今回紹介した親族外承継の知識を活かし、早期に事業承継計画を立てることから始めましょう。
まずは現在の会社の状況を正確に把握し、社内外から適切な後継者候補を選定してください。
そして税理士、弁護士、経営コンサルタントなどの専門家に相談し、最適な承継方法を検討することが重要です。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
親族外承継は、経営能力や意欲を重視した後継者選定ができる一方で、関係者からの理解獲得や個人保証の引き継ぎなど、多くの課題を抱えています。
一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、こうした後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。
JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。
事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。