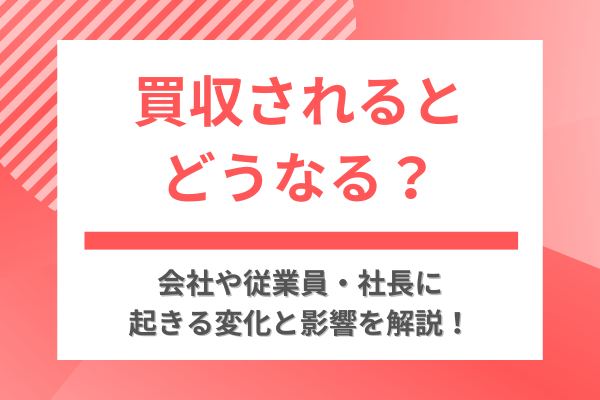「買収されると会社はどうなる?」
「売り手企業の社長や社員の待遇は?」
会社が買収されると、買い手企業の経営方針やM&Aのスキームによって組織や人事制度に変化が起こる可能性があります。
ただし、「買収=終わり」ではなく、多くの場合は従業員の雇用が継続され、福利厚生の充実や昇進のチャンス拡大など、以前より良い環境につながるケースも少なくありません。
実際に、後継者不足や資金面に課題を抱えていた企業が買収を受けたことで、経営の不安が解消され、従業員の雇用が守られた事例や、新たな事業展開によって活躍の場が広がったケースも多く見られます。
本記事は、「買収後の会社に起こる変化」や「社長・役員・社員それぞれの処遇」について詳しく解説します。
これからM&Aを検討している経営者の方や、買収される側として不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
監修者

代表理事
小野 俊法
経歴
慶應義塾大学 経済学部 卒業
一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。
その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。
その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。
投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。
会社が買収されるとどうなる?影響を決める3つの要因
会社が買収された際の影響を左右する主な要因は、「買い手企業の方針」「買収の目的」「M&Aのスキーム」の3つです。
一口に買収といっても、すべての企業で同じ変化が起こるわけではなく、これらの条件次第で会社や社員への影響は大きく異なります。
例えば、買い手企業が既存事業の強化やシナジー創出を目的としている場合、現在の経営体制や人材を尊重し、組織や雇用を維持するケースが多く見られます。
一方、再建を目的とした買収では、経営陣の交代や人事制度の見直し、業務プロセスの改革など、比較的大きな変化が生じることもあります。
このように、買収後に起こる変化を正しく理解するためには、「買い手企業の方針」「買収の目的」「M&Aのスキーム」という3つの要因を総合的に確認することが重要です。
買収後の会社に生じる組織・経営の変化
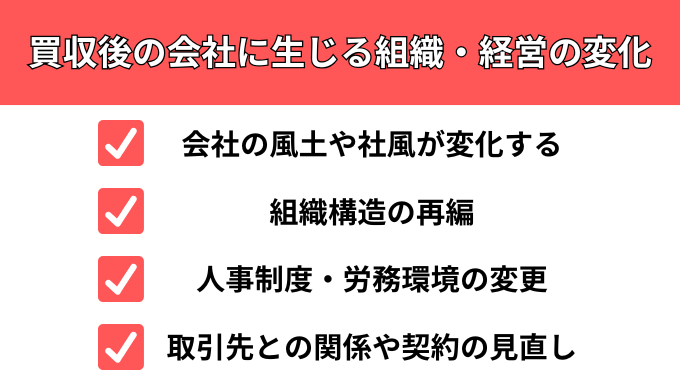
買収後の組織・経営変化は以下の通りです。
- 会社の風土や社風が変化する
- 組織構造の再編が行われる
- 人事制度・労務環境の変更が実施される
- 取引先との関係や契約の見直し
買収が実行されると、新しい企業文化や経営方針が取り入れられることで、従来の働き方や職場環境に変化が生まれます。
買収後の変化は避けられないものですが、事前に内容を把握しておくことで、社員の不安や混乱を軽減することが可能です。
それでは上記の組織・経営変化について解説していきます。

会社の風土や社風が変化する
買収により、今までの会社の風土や社風が大きく変化する場合があります。
そのため、異なる文化や価値観を持つ企業が一つになることで、新しい発想や多様な働き方が取り入れられるケースも多くあります。
買い手企業の方針が加わることで、従来にはなかった成長のチャンスが広がる可能性があります。
主な変化の例は以下の通りです。
| 社風・風土の変化例 | 詳細 |
|---|---|
| 経営方針の変更 | 意思決定のスピードが上がり、効率的な進行が可能になる |
| 評価制度の刷新 | 成果主義の導入により、努力や実績が評価されやすくなる |
| 社内のやりとり | グローバルなコミュニケーションスタイルが加わり、視野が広がる |
上記の変化は、新たな成長機会を生み出すきっかけになります。
社員が安心して適応できるようにするためには、経営陣が透明性を持って情報を共有し、社員と積極的に対話を重ねることが大切です。
組織構造の再編
買収によって新しい経営陣や親会社の方針が導入され、役割分担や意思決定ルートなど、職場環境が根本的に見直されます。
新しい仕組みやルールに慣れるまでに時間がかかることはありますが、効率化や成長のチャンスにつながるケースも多いです。
| 再編内容 | 主な変化 |
|---|---|
| 部署再編・統合 | 重複部署の整理や配置の最適化によって効率化が進む |
| ガバナンス体制の変更 | 意思決定ルートやルールがより明確になる |
| 業務プロセス・制度の変更 | 社内ルールや手順が改善され、生産性向上が期待できる |
たとえば、買収によって役員や社員のポジション、業務内容、配属先が再検討されることもありますが、これは単なる入れ替えではなく、将来的な成長や新しいキャリアの広がりを意図したものです。
特に株式譲渡による買収では、新しい経営体制が加わることで、新しいノウハウや資金力が取り入れられ、さらなる発展につながる可能性があります。
人事制度・労務環境の変更
買収後は、買い手企業の方針や人事制度に合わせて統一が図られることで、働く環境がより整備されるケースが多いです。
新しいルールや評価基準は、社員の成長を促し、公平性を高める仕組みとして導入されることが一般的です。
また、勤怠管理や人事評価、福利厚生などが改善される例もあります。
大企業の仕組みが導入されることで、より透明性の高い制度や充実した福利厚生を受けられる可能性があります。
| 変更内容 | 詳細 |
|---|---|
| 勤怠管理 | システム導入で効率化・労務環境の改善 |
| 人事評価制度 | 透明性のある評価基準で昇進・昇給の機会が拡大 |
| 福利厚生の見直し | 保険・手当・休暇制度の充実 |
| 賃金・賞与制度 | 明確な給与テーブルで将来設計が立てやすい |
| 配置・異動 | キャリアアップのための異動や新しい挑戦の機会 |
新しい制度に慣れるまでは戸惑うこともありますが、システムや評価基準が整うことで、長期的には働きやすさや公平性が高まるケースが多く見られます。
これまでの働き方が尊重されつつも、買い手企業の制度が段階的に導入されることで、より良い労務環境や成長の機会が得られることが期待できます。

取引先との関係や契約の見直し
買収後は取引先との契約関係が大きく変わるため、譲渡する企業は事前に契約内容を確認し、適切な対応を取る必要があります。
株式譲渡では会社自体は存続するため、取引先との契約や許認可は原則そのまま引き継がれます。
一方で、契約書にチェンジ・オブ・コントロール条項があると、経営権の移動を理由に契約の見直しや解除を求められる場合があります。
事業譲渡では契約が自動では承継されないため、重要な取引先とは買い手と連携しながら再契約や条件調整を進める必要があります。
| スキーム | 契約の引き継ぎ | 注意点 |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 譲受企業が契約をそのまま引き継ぐ | チェンジオブコントロール条項がある場合、取引先から承諾が必要 |
| 事業譲渡 | 契約関係は引き継がれない | 取引先ごとに契約上の地位の移転手続きが必要 |
上の表のように、自社がどのスキームで承継するのかを確認し、契約ごとに「自動承継か」「取引先の同意や再契約が必要か」を洗い出しておくと、買収後の交渉がスムーズになります。
特に売上比率の高い取引先には、旧オーナーから新経営陣を紹介し、今後の方針やサポート内容を丁寧に伝えることで、関係悪化のリスクを下げられます。
買収された後に統合を成功させるポイント
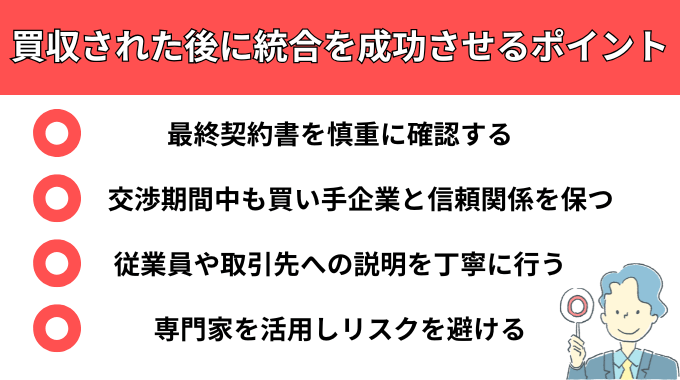
会社売却を成功に導くためのポイントは、以下の通りです。
- 最終契約書を慎重に確認する
- 交渉期間中も買い手企業と信頼関係を保つ
- 従業員や取引先への説明を丁寧に行う
- 専門家を活用しリスクを避ける
会社売却は企業の将来を左右する重要な決断であり、適切な準備と専門知識なしには成功は困難です。
特に最終契約書の内容確認、関係者への丁寧な説明、そして各分野の専門家との連携は、売却を成功に導く上で欠かすことのできない要素となります。
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
最終契約書を慎重に確認する
最終契約書を慎重に確認することは、会社売却を成功に導く重要なポイントです。
最終契約書(DA)は基本合意書とは異なり、記載されたすべての内容に法的拘束力が発生します。
契約違反があった場合には損害賠償請求や契約破棄の対象となるため、条件を慎重に検討することが重要です。
確認すべき重要項目と注意点
| 項目 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 表明保証 | 財務状況や法令遵守等の真実性 | 事実と異なる場合は損害賠償責任が発生 |
| 従業員保護 | 雇用契約承継と労働条件維持 | 全従業員の雇用継続を明記することが重要 |
| 補償条項 | 賠償責任の範囲と期間設定 | 通常は譲渡価格の一定%まで、期間は1-2年 |
| 競業避止義務 | 同業種での再起業制限範囲 | 地域・期間・業種の制限範囲を明確化 |
会社分割の場合は労働契約承継法に基づく承継の取扱いを明記します。
株式譲渡では法人同一のため雇用はそのまま存続、事業譲渡では転籍同意や労働条件維持の取り決めを契約条項で明確化します。
したがって、最終契約書を慎重に確認することで、自社の社員や役員を守り、買収先の意向も汲んだ条件での売却が可能となり、会社売却の成功につながるのです。

交渉期間中も買い手企業と信頼関係を保つ
買収後の統合を成功させるために、交渉期間中から買い手企業と信頼関係を保つことが重要です。
価格だけを巡って対立すると、クロージング後も本音を言い合えず、現場の協力が得にくくなるからです。
そこで、良い情報だけでなくリスクや弱みも正直に開示し、相手の懸念や譲れない条件を丁寧に聞き取る姿勢が大切といえます。
たとえば、従業員の処遇や企業文化について早い段階から話し合い、合意した内容は必ず期限どおりに実行します。
交渉中から「約束を守る相手」として信頼を積み重ねておけば、買収後のコミュニケーションもスムーズになり、統合に伴う不安を小さくできるでしょう。
結果として、従業員や取引先にも一貫したメッセージを出しやすくなり、信頼を損なわずに統合を進められます。
従業員や取引先への説明を丁寧に行う
会社売却を成功に導くには、従業員や取引先への丁寧な説明が重要です。
適切な情報開示により不安を解消し、M&A後の円滑な統合を実現することができます。
会社売却時の説明を成功させるために必要な要素を以下の表にまとめました。
従業員への説明では、以下の不安要素に必ず回答する必要があります。
一般的に従業員は給与や地位、転勤の可能性について強い関心を持っているため、上記の点について明確な回答を用意することが必要です。
また、取引先に対しては、売り手と買い手が揃って訪問し、事業継続性と今後の関係維持について説明することが重要です。
通常はクロージング後に報告を行いますが、重要な取引先には基本合意後の事前説明も検討しましょう。
専門家を活用しリスクを避ける
会社売却の際は、M&A仲介会社、公認会計士、弁護士、税理士などの専門家が連携することで、複雑なプロセスに潜むリスクを回避できます。
M&Aは高度な専門知識と豊富な経験が必要なため、素人だけでは最適な結果を得ることは困難です。
各分野の専門家が連携することで、売却プロセスの各段階で最適な判断を行えます。
| 専門家の役割 | 主な業務内容 |
|---|---|
| M&A仲介会社 | 買い手企業の選定 交渉 クロージング全般をサポート |
| 公認会計士 | 企業価値評価 デューデリジェンス対応 適正価格算定 |
| 弁護士 | 契約書作成・レビュー 法的リスク排除 従業員保護条項設定 |
| 税理士 | 売却に伴う税務処理最適化 手取り額最大化 |
専門家との連携により、財務リスク、法務リスク、経営リスクなど多様なリスクに対応できます。
特に、デューデリジェンスを専門家に依頼することで、簿外債務や偶発債務などの潜在的リスクを事前に検出し、適切な対策を講じることが可能です。
また、過去の実績に基づいて潜在的なリスクやデメリットを事前に洗い出し、具体的な対策を立案・実行するサポートを提供してくれます。
このように、専門家との連携により、想定外の問題が発生した場合にも適切な対応が可能になり、売却プロセス全体の成功確率を大幅に向上させることができます。
買収された会社の社長はどうなるのか?
では、会社が買収された後に社長はどのような立場になるのでしょうか。
実際の事例や中小企業のM&A現場を見てみると、以下のようなパターンが多く見られます。
- すぐに退任・引退する
- 引き継ぎ後に退任する
- 継続して社長を務める
どのパターンになるかは、買収の目的や社長本人の意思、買収側企業との協議結果によって異なります。
すぐに退任・引退する
買収された会社の社長は「すぐに退任・引退する」ケースが多いです。
買収後に社長が退任・引退する主な理由は、後継者不在の問題や十分な売却益を得たため次の人生に進みたいという本人の希望があるためです。
また、買収という大きな経営の節目を機に、これまでの役目を終えたと感じる経営者が多いことも背景です。
例えば有名な事例として、ZOZO創業者の前澤友作氏はヤフーによる株式買収のタイミングで社長職を退任し、新しい分野で活躍をはじめています。
また多くの中小企業M&Aでも、オーナー社長が事実上「すぐに引退」することは一般的です。
引き継ぎ後に退任する
買収された会社の社長は引き継ぎを終えてから退任するのが一般的です。
引き継ぎが適切に行われないと新体制への移行がスムーズに進まず、経営や現場に混乱を招く恐れがあるためです。
特に中小企業やワンマン経営だった場合は、社長のノウハウや人脈の伝承が重要視されます。
買収契約後に「キーマン条項」を設け、社長が一定期間会社に残って引き継ぎや業務支援を続けるケースが多く見られます。
引き継ぎ期間は、会社や業界によって異なりますが、数か月から数年に及ぶこともあります。
継続して社長を務める
買収された会社の社長が継続して務めるケースも珍しくありません。
新しい経営体制に円滑に移行するため、買い手企業がこれまでの社長にしばらく経営を任せたいと考える場合があるためです。
また、会社や従業員の成長を見届けたいという社長自身の希望が尊重されるケースも多いです。
例えば、会社売却後に子会社として存続する場合は、元の社長がそのまま経営を担うことが多いです。
事業の引継ぎや成長戦略を進める中で、これまでの社長が引き続きリーダーとして求められる場面が多数あります。

買収された会社の役員はどうなるのか?
会社が買収されると、役員の立場や役割がどう変わるのか気になる方は多いでしょう。
買収後は、新しい経営方針や組織体制に合わせて役員の処遇が見直されることがありますが、その対応はケースバイケースです。
退任・引退となる場合もあれば、一定期間は引継ぎや経営サポートを担い、その後新たな役割に就くケースもあります。
以下に詳しく説明します。
買収後も役員として継続する
買収された会社の役員が、買収後も役員として継続するケースは多く見られます。
買収側は現場や人材の安定を重視するため、実力が認められている役員は買収後も引き続き重要なポジションで活躍できます。
また、引き継ぎや事業のスムーズな統合を目的に、一定期間継続を条件とすることも珍しくありません。
たとえば、買収前から会社の成長に大きく貢献していた役員は「組織の要」として、買収後も経営に参画し続けています。
一方で、経営方針が大きく変わり本人が納得いかない場合は退職を選ぶ例もあります。
退任・引退する
買収された会社の役員は、退任や引退となる場合があります。
これは、買収によって経営権や方針が新たな買い手企業に引き継がれ、旧経営陣がそのまま残るとスムーズな組織改革や新体制の構築が難しくなることが理由です。
特に親族役員の場合は、交代が条件となるケースが少なくありません。
一方で、PMI(経営統合プロセス)を円滑に進めるため、一時的に引継ぎ役や顧問として残るケースもあります。
つまり、買収された会社の役員は新体制づくりや引継ぎ状況によって処遇が異なり、退任・引退となることが多いものの、継続する場合もあります。
買収された会社の社員はどうなるのか?
M&A(合併・買収)が行われた後も、解雇には法律上の厳しい制限があるため、合理的な理由なく一方的に雇用を打ち切られることは原則として認められていません。
その結果、多くの場合は社員の雇用が継続されます。
新しい経営資源やノウハウが導入されることで、キャリアアップやスキル向上の機会が広がります。
買収企業の人事制度や福利厚生が導入されることで、働きやすさを実感できるケースも少なくありません。
もちろん変化に適応する柔軟さは必要ですが、M&Aは「終わり」ではなく「新しいスタート」として捉えることができます。
そのまま雇用が継続する
多くのM&A(合併・買収)では、社員の雇用契約は基本的に変更なく継続されます。
買収側の企業は事業の継続性やノウハウの維持を重視しており、社員の知識やスキルが不可欠です。
法律(労働契約法など)でも、正当な理由なく従業員を解雇することは制限されています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法第16条
特に株式譲渡の場合は法人格が変わらず、雇用契約や就業規則もそのまま引き継がれるケースが多いでしょう。
一方、事業譲渡型のM&Aでは、事業単位で新会社に移転するため、従業員は新たな雇用契約を結ぶ必要があります。
ただし、本人の同意が前提となるため、合意がなければ転籍は成立しません。
待遇や業務が変更される場合がある
買収後は、会社の方針や統合プロセスに応じて、一部の社員で待遇や業務内容が見直される場合があります。
一方で、大きな変更が生じないケースも少なくありません。
変更が行われる際も、組織の生産性向上や働きやすさの向上を目的として、段階的に進められるのが一般的です。
主に検討され得る見直しの例は次のとおりです。
| 変更される項目 | 詳細 |
|---|---|
| 給与や賞与 | 買収企業の給与体系に合わせて見直されることがある |
| 業務内容 | 既存の業務から新しい分野や役割を担当する場合がある |
| 勤務地や部署 | 他拠点や別部署への異動や転勤を命じられることがある |
| 人事評価制度 | 買収先の新しい評価基準が導入されるケースが多い |
上記の見直しにより、キャリアの幅が広がる・評価の基準が明確になる・福利厚生や制度が整うなど、プラスの効果が期待できることも多くあります。
社員の立場としては、今後の待遇や業務内容について十分な情報を集め、新しい環境に柔軟に対応することが重要です。
退職する
買収だけで即時解雇されることは基本的にありませんが、待遇や環境の変化をきっかけに退職を選ぶ人もいます。
- 会社の方針や社風が大きく変わることに不安を感じたとき
- 給与や待遇、勤務地などの労働条件が変わった場合
- 社長や役員など経営陣が異動・交代し、信頼関係に不安を感じるとき
- 新しい職場環境になじめず、ストレスを感じるケース
社員自身の判断で退職を選ぶ場合、原則は「自己都合退職」扱いとなります。
ただし、条件悪化が著しく実質的な退職勧奨や解雇相当と判断される場合等には、会社都合に準じた扱い(特定受給資格者の範囲)となる可能性があります。
会社から不利益な変更があった場合は、条件や制度について十分に説明を受け、不安な点は専門家に相談するのが安全です。
会社が買収される際のよくある質問
会社が買収される際に寄せられる、よくある質問集を紹介します。
- 買収される側の会社や社員にとってのデメリットは?
- 買収後にリストラや人員整理が行われるケースは多いのですか?
- 買収後の社員のボーナス(賞与)や給料はどうなる?
- 買収された会社の社員はリストラされやすいのか?
- 投資ファンドに買収されると会社と社員はどうなる?
M&Aや企業買収を検討している方、また買収される側の立場に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
買収される側の会社や社員にとってのデメリットは?
買収される側の会社や社員にとってのデメリットは、主に「待遇や環境の変化による不安やストレスが増える」ことです。
経営方針や組織、人事制度が大きく変わる場合が多く、人材流出やモチベーション低下、最悪の場合はリストラや待遇悪化のリスクも生まれるためです。
例えば、買収後に異動命令や給与体系の見直しが行われ、転勤を命じられることや、従業員間の摩擦で働きにくくなるケースが挙げられます。
買収後にリストラや人員整理が行われるケースは多いのですか?
買収後にリストラや人員整理が行われるケースは多くありませんが、一定のケースでは実施されることがあります。
日本企業では買収後も従業員の雇用が維持されることが多く、法律的にも整理解雇の要件が厳しいため、簡単にリストラが起きることは少ないです。
しかし、経営合理化や業績悪化、新会社の方針への不適応などで人員整理が検討される場合もあります。
買収後の社員のボーナス(賞与)や給料はどうなる?
買収後の社員のボーナス(賞与)は、原則として従来通り支給が維持されることが多いですが、事業譲渡や就業規則の変更を伴う場合は内容が見直されることもあります。
特に株式譲渡によるM&Aでは雇用契約がそのまま引き継がれるため、賞与の支給条件や計算方法は基本的に変わりません。
一方、事業譲渡型では新たな雇用契約となるため、買収先の就業規則や人事制度へ移行する際に、ボーナスの支給時期や金額が変更されることがあります。
また会計年度の調整などで一時的に算定期間が短縮され、初年度のみ支給額が減るケースも見られます。
買収された会社の社員はリストラされやすいのか?
買収された会社の社員がリストラされやすいかどうかは、基本的には「買収側企業の考え方次第」となりますが、日本では雇用が維持されるケースが多くなっています。
株式譲渡による買収では、社員の雇用契約がそのまま引き継がれるため、買収直後にリストラされることは基本的にありません。
日本では整理解雇の法律要件が厳しいため、簡単にリストラが起きることは少なく、むしろ給与などの待遇が改善される可能性もあります。
ただし例外的に、買収後に社員が新しい会社の方針に適応できなかったり、経営統合後に業績が悪化して人件費圧縮が必要になったりした場合には、リストラの対象となる可能性があります。
投資ファンドに買収されると会社と社員はどうなる?
投資ファンドに買収されると、会社は資金調達や経営支援を受けられる一方で、従業員の待遇変更や事業再編が実施される可能性があります。
必ずしもマイナスの影響だけではなく、企業価値向上により雇用が安定するケースも多く見られます。
| 項目 | 変化の内容 |
|---|---|
| 経営体制 | 社外取締役やファイナンシャル・アドバイザーが経営に参加し、成長戦略を推進 |
| 事業方針 | 収益性の低い事業は縮小・売却され、主力事業への集中が図られる |
| 資金調達 | ファンドからの資金投入により、設備投資や市場拡大が可能になる |
| 社風・企業文化 | 買収側の経営方針に合わせて変化する可能性がある |
従業員については、法律により解雇は原則として認められていません。
ただし、労働条件や待遇には変更が生じる場合があります。
給与体系や評価制度が買収企業の基準に統合されるケースが多く、福利厚生の内容も見直されることがあるでしょう。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
M&Aや経営統合の場面では、経営方針の変化や役員・従業員の処遇など、多くの不安が生じます。
特に後継者不足や承継後の経営安定に悩む経営者の方にとって、適切な相談相手を見つけることが重要です。
日本プロ経営者協会は、国内最大級のプロ経営者ネットワークを活用し、中小企業からクリニックまで幅広い事業承継に実績を持つ組織です。
株式譲渡や合併といったM&Aスキーム選定から、承継後の経営方針策定、社員の雇用や待遇調整に至るまで、専門的な知見でサポートいたします。
将来にわたって安心できる事業承継を実現するために、ぜひ日本プロ経営者協会へご相談ください。
JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。
JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |
|---|---|
| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |
| 設立日 | 2019年7月 |
| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |
| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |
| URL | https://www.proceo.jp/ |
まとめ
買収後の会社の運命は、買い手企業の経営方針やM&A手法、そして関係性によって大きく左右されます。
社長や役員の処遇、社員の雇用や待遇、会社の文化や人事制度までもが買い手の意向で変化する可能性があります。
そのため、買収後の変化を正しく理解し、事前に対策を立てておくことが安心につながります。
今回紹介したポイントを踏まえ、M&Aを検討している経営者や社員の方は、買い手企業の方針やスキームをしっかり確認し、情報収集を怠らないよう意識してみてください。
特に「雇用や待遇がどうなるのか」を把握することは、今後の働き方や人生設計を考えるうえで重要です。