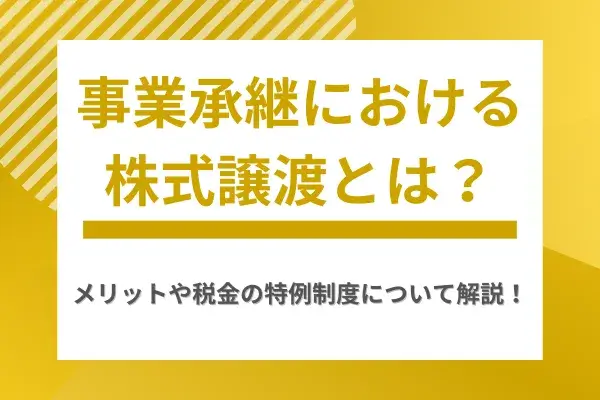「事業承継の株式譲渡とは?」
「事業承継における株式譲渡のメリットとは?」
事業承継における株式譲渡とは、現経営者が保有する株式を後継者に移転することで経営権を引き継ぐ手法です。
株式譲渡には生前贈与、相続、売買の3つの方法があり、それぞれ異なる税制が適用されます。
- 売却益を獲得できる
- 事業を存続・継続できる
- 従業員の雇用を維持できる
今回は、「事業承継における株式譲渡の種類と特徴」や「事業承継における株式譲渡のメリット・デメリット」について詳しく解説していきます。
事業承継を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
監修者

代表理事
小野 俊法
経歴
慶應義塾大学 経済学部 卒業
一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。
その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。
その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。
投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。
事業承継における株式譲渡とは?
事業承継における株式譲渡とは、会社の経営権を後継者や第三者に引き継ぐために、自社の株式を譲り渡す方法です。
中小企業の事業承継では最も一般的な手段であり、会社を解散せずにそのまま存続できるのが大きな特徴です。
株式を譲渡することで、会社の資産や契約、従業員、取引先との関係をそのまま引き継ぎながら、経営権だけを新しい経営者に移すことができます。
そのため、事業への影響を最小限に抑えつつ、スムーズな承継が可能になります。
たとえば、創業者が保有する株式を子どもや社員、あるいは外部の企業に譲ることで、会社の経営権が新たな所有者へと移転します。
手続きが比較的簡単で、税制上の優遇措置を受けられる場合も多いため、株式譲渡は事業を止めずに未来へつなぐ実践的な承継方法といえます。

株主の権利
株主の権利とは、会社に出資した人が持つ「会社への参加権」や「利益を受け取る権利」のことです。
株主は会社の「所有者」として位置づけられており、出資した金額や持ち株数に応じて経営への影響力を持ちます。
そのため、後継者が株を譲り受けることで、経営権や意思決定権も同時に受け継がれるのです。
| 株主の主な権利 | 内容 |
|---|---|
| 配当を受ける権利 | 会社の利益を受け取る権利 |
| 残余財産の分配を受ける権利 | 解散時の残り資産を受け取る権利 |
| 議決権 | 株主総会で経営に関する意思決定を行う権利 |
たとえば、株主は利益が出た際に配当を受けることができます。
また、会社が解散する際には、残った財産を分配してもらう権利もあります。
さらに、株主総会では取締役の選任や利益処分の決定などに参加し、重要な経営判断に関与します。
なお、持ち株数が多いほど、影響力のある議決権を多く持つことになります。
事業承継における株式譲渡の種類

事業承継における株式譲渡の種類は、以下の通りです。
| 種類 | 税制 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 贈与税 | 年間110万円の基礎控除活用可能 |
| 相続 | 相続税 | 基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」 |
| 売買 | 譲渡所得税 | 現経営者の老後資金確保が可能 |
それぞれの特徴を解説していきます。
生前贈与
生前贈与は、現経営者が生きているうちに後継者へ無償で株式を渡す方法です。
- 後継者が株式を取得するための資金を用意する必要がない
- 現経営者が存命のうちに事業承継の計画を立てられるため、入念な税金対策を講じることができる
- 年間110万円までの基礎控除を活用すれば、贈与税を抑えながら計画的に株式を移転できる
年間110万円以内で複数年に分けて株式贈与を行えば、受贈者の税負担を減らすことが可能です。
また、相続時精算課税制度を利用すれば、累計2,500万円までの財産贈与が非課税になります。
親族内承継で多く利用されており、贈与契約書を作成して無償で株式を譲渡します。
このように、生前贈与は資金負担がなく、計画的な税金対策ができるため、事業承継における株式譲渡の最適な選択肢です。
相続
相続は、現経営者が亡くなった後に自動的に株式が後継者に移転される事業承継の方法です。
- 後継者の資金負担がない
- 相続税の基礎控除が利用でき、税負担を軽減できる
- 法的手続きが簡単で、遺産分割協議書の作成により株式移転が完了する
相続では、基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。
法定相続人が3人の場合、4,800万円までの財産は非課税となります。また、事業承継税制を活用すれば、後継者が承継する自社株式の相続税を猶予または免除できます。
親族内承継で最も多く活用されており、遺言書や遺産分割協議により株式の承継先を決定します。
事業承継税制は、後継者が贈与や相続によって非上場株式等を取得した場合、要件を満たすことで贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けられる特例制度です。
売買
売買は、現経営者が後継者に対価をもらって株式を譲り渡す方法です。
- 現経営者が株式譲渡の対価を受け取れるため、老後の資金を確保できる
- 後継者に経営への責任感を持たせることができる
株式の売買では、適正な価格での取引が重要になります。親族内承継でも社内承継でも活用でき、分割払いや役員退職金との組み合わせにより後継者の資金負担を軽減できます。
また、第三者承継の場合は、M&Aによる株式売買が一般的で、企業価値に基づいた適正価格での取引が行われます。
売買は対価を受け取れる点で現経営者にメリットがある一方、後継者には資金調達の負担が生じるため、計画的な準備が必要になります。
事業承継の種類
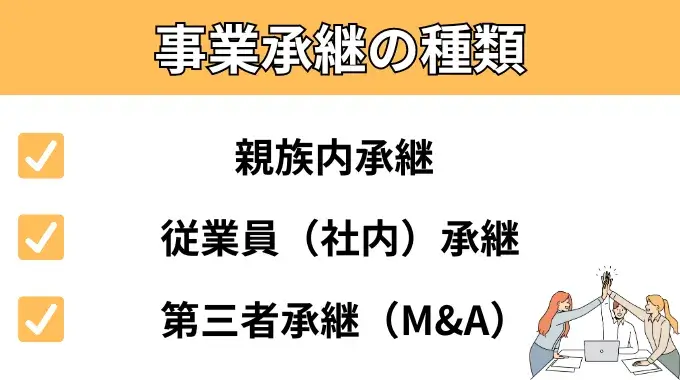
事業承継には、大きく分けて3つの方法があります。
| 種類 | 承継先 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 親族内承継 | 子どもや兄弟姉妹など | 経営理念の維持がしやすく、長期的な育成が可能 |
| 従業員(社内)承継 | 役員や従業員 | 引き継ぎがスムーズで、現場の理解を得やすい |
| 第三者承継(M&A) | 社外の企業や個人 | 後継者不在でも承継可能で、売却益も得られる |
それぞれの承継方法には異なるメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて最適な選択をすることが重要です。
以下では、各承継方法について解説していきます。
親族内承継
親族内承継とは、経営者が自分の子どもや兄弟姉妹など、血縁関係にある親族へ事業を引き継ぐ方法です。
親族内承継は、家族間で信頼関係があるため、経営方針や社風の維持がしやすく、従業員や取引先にも安心感を与えられます。
また、早い段階から後継者教育ができるため、事業運営の継続性が高まります。
たとえば、製造業を営む父親が息子に経営を引き継ぐケースでは、若いうちから現場を経験させることで、経営者として必要な知識や信頼を積み上げることができます。
一方で、兄弟間で後継者争いが起きたり、遺産分割でもめる可能性もあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、早めに遺言書や株式の承継計画を作っておくことが重要です。
従業員(社内)承継
従業員(社内)承継とは、社内の信頼できる役員や従業員の中から次期経営者を選び、事業を引き継ぐ方法です。
従業員承継は、社内にいる実績のある人に経営を託すことができ、現場の賛同を得やすい事業承継方法です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 引き継ぎがスムーズに進む | 後継者が株式取得資金など負担を背負う |
| 従業員や取引先の納得が得やすい | 候補者間でトラブルとなる可能性がある |
| 実績や人柄を判断しやすい | 辞退されることもある |
このように、従業員承継は社内事情をよく知る人材にスムーズに事業を託せる一方で、後継者への資金負担や候補者間の調整も必要となる方法です。
第三者承継(M&A)
第三者承継(M&A)とは、親族や従業員以外の第三者に会社や事業を引き継ぐ方法のことです。
第三者承継は、親族や従業員の中に適任者が見つからない場合でも、社外の企業や起業希望者に経営を引き継げる仕組みです。
実際には、株式譲渡や事業譲渡の形で行われ、譲渡後も社名や取引関係が維持されることが多く、スムーズな経営移行が可能です。
例えば、長年地元で続いた老舗飲食店が、後継者不足により廃業を考えていたところ、同業の外部企業にM&Aで引き継いだ結果、店舗とスタッフがそのまま存続したという事例があります。
このように、第三者承継(M&A)は、後継者が社内外に見つからない企業にとって、事業の継続と雇用の維持を両立できる承継方法です。
事業承継における株式譲渡のメリット(売り手)
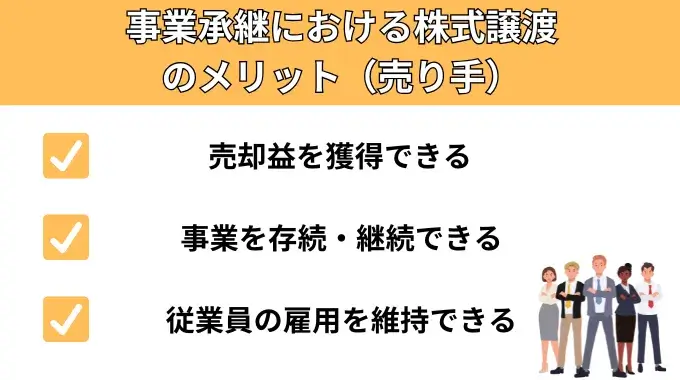
事業承継における株式譲渡のメリット(売り手)は以下の通りです。
- 売却益を獲得できる
- 事業を存続・継続できる
- 従業員の雇用を維持できる
それでは上記のメリットについて解説していきます。
売却益を獲得できる
事業承継で株式譲渡を選ぶと、経営者はまとまった売却益を手に入れることができます。
株式譲渡では、経営者が保有する株式を買い手に売却することで、対価として現金を受け取れるからです。
事業譲渡とは異なり、売却代金は会社ではなく株主である経営者個人に直接支払われます。
また、売却益にかかる税金は所得税や住民税のみで、法人税よりも税負担を抑えられる点も大きなメリットとなります。
事業を存続・継続できる
株式譲渡により事業を存続・継続できることは、売り手にとって最大のメリットです。
株式の保有者が新しくなるだけで、会社としての事業活動や従業員、取引先との関係などは変わることなく引き継がれます。
廃業を選んだ場合、費用がかかるだけでなく、従業員の失業も避けられません。
しかし株式譲渡で他の企業に経営権を移転させれば、株主は変わりますが従業員の生活を守ることができます。
従業員の雇用を維持できる
事業承継で株式譲渡を選ぶと、従業員の雇用を維持できます。
株式譲渡では、会社の所有者が変わるだけで、従業員との雇用契約はそのまま引き継がれるからです。
事業譲渡とは異なり、従業員一人ひとりの個別同意も必要ありません。
会社組織自体に変更がないため、給与や労働条件もそのまま継続され、従業員にとって安心な環境が保たれます。
事業承継における株式譲渡のデメリット(売り手)
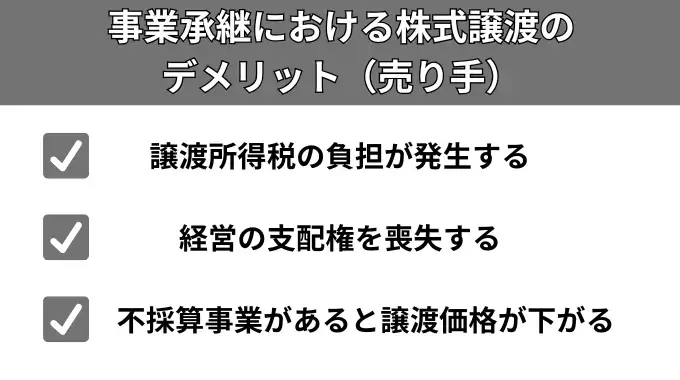
事業承継における株式譲渡にはデメリットも存在します。
- 譲渡所得税の負担が発生する
- 経営の支配権を喪失する
- 不採算事業があると譲渡価格が下がる
ここでは、売り手側が注意すべき代表的なデメリット3つを詳しく解説します。
譲渡所得税の負担が発生する
事業承継で株式譲渡を選択すると、売り手には必ず譲渡所得税が課税されます。
株式を売却して得た利益は、譲渡所得として所得税の課税対象になるためです。
個人株主の場合、譲渡所得税の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)となっています。
さらに、株式譲渡は分離課税方式で計算されるため、他の所得とは別に税金を納める必要があります。
贈与や相続による事業承継とは異なり、売買による譲渡では避けることのできない税負担となります。
1億円で株式を譲渡し、取得費や手数料が1,000万円だった場合、譲渡所得は9000万円となります。
このとき発生する譲渡所得税は約1,828万円(9,000万円×20.315%)になります。
経営の支配権を喪失する
事業承継で株式譲渡を選択すると、経営の支配権を完全に失ってしまいます。
株式の過半数を保有することは、会社の経営権を握ることを意味します。
株式譲渡により過半数の株式を譲渡すれば、取締役の選任・解任などの普通決議事項についての決定権を失います。
また、2/3以上を譲渡した場合、定款変更や合併などの特別決議事項についても決定権を失います。
売り手側は対象企業に対する支配権を完全に失い、今後の経営に関与できなくなってしまいます。
不採算事業があると譲渡価格が下がる
事業承継で株式譲渡を行う際、会社に不採算事業が含まれていると譲渡価格が大幅に下がってしまいます。
株式譲渡では会社全体を丸ごと引き継ぐため、採算の取れない事業も買い手が承継する必要があります。
買い手は不採算事業によるリスクを考慮し、企業価値を低く評価してしまうのです。
事業譲渡と異なり、一部の事業だけを切り離すことができないため、マイナス評価を受けやすくなります。
事業承継における株式譲渡の手順
中小企業では株式に譲渡制限が設けられているため、自由に譲渡することができません。
会社法に従った適切な手続きを行わなければ、譲渡が承認されない場合があります。
そのため、段階的な手順を踏むことが不可欠になります。
事業承継における株式譲渡の手順
現経営者が会社に対して株式譲渡承認請求書を提出します。書類には譲渡する株式の種類や数、後継者の氏名などを記載する必要があります。
会社は取締役会(設置していない場合は株主総会)を開催し、承認の決議を行います。中小企業では株主総会での決議が多くなります。
会社は承認請求から2週間以内に、決定内容を請求者に通知します。期間内に通知がない場合、承認されたものとみなされます。
承認を得た後、譲渡する側と受ける側で株式譲渡契約を結びます。生前贈与の場合は贈与契約書になります。
株式譲渡後、会社の株主名簿を書き換える手続きを行います。多くの会社で株券が発行されていないため、株主名簿の記載が権利主張に必要になります。
※株券不発行会社の場合、株主名簿の名義書換えを行うことで、第三者に対して株主であることを主張できるようになります
最後に株式譲渡対価の支払いを行い、手続きが完了します。
上記のプロセスを踏むことで、家族や会社を守る事業承継につながります。
予期せぬトラブルを避けるためにも、しっかり流れを理解し、手続きしてください。
株式譲渡にかかる税金
事業承継で売買による株式譲渡をおこなう場合、譲渡する人には一律20.315%の税金がかかります。
株式を売却して得た利益に対して所得税・住民税・復興特別所得税が課税されるためです。
株式譲渡による利益は譲渡所得として扱われ、他の所得とは分けて計算する「分離課税」方式が適用されます。
株式の売却価格から取得費用や手数料を差し引いた譲渡益に対して課税される仕組みです。
1,000万円で株式を売却し、取得費が300万円、手数料が50万円だった場合
- 譲渡益:1,000万円 – 350万円 = 650万円
- 税額:650万円 × 20.315% = 約132万円
事業承継における株式譲渡の税金一覧
| 税金の種類 | 税率 | 課税対象者 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 個人の株式売却者 |
| 住民税 | 5% | 個人の株式売却者 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 個人の株式売却者 |
| 合計 | 20.315% | 個人の株式売却者 |
| 法人税等 | 約30~34% | 法人の株式売却者 |
※個人が株式を売却した場合の税率
※法人が売却した場合は実効税率が適用
計画的な準備により節税対策も可能ですので、専門家への相談をおすすめします。
参考:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
株式譲渡に活用できる特例事業承継税制とは
特例事業承継税制は、中小企業の株式譲渡による事業承継時に、全株式に対して贈与税・相続税を100%猶予し、最終的には免除も可能となる制度です。
ただし、継続要件や報告義務など厳格な制約があるため、制度の内容を正しく理解した上で活用することが重要です。
以下では、特例事業承継税制の概要・要件・注意点について解説していきます。
特例事業承継税制の概要
事業承継税制は、中小企業が次の世代へ事業を引き継ぐ際に、非上場株式の贈与税や相続税の負担を軽減する制度です。
株式譲渡で会社を引き継ぐ際、株価が高額になると多額の税金が発生しますが、この制度を使えば納税を猶予し、一定条件を満たせば最終的に免除されます。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 適用期限 | なし | 令和9年12月31日まで |
| 対象株式数 | 総株式の3分の2まで | 全株式 |
| 猶予割合 | 贈与税100%、相続税80% | 100% |
| 後継者の人数 | 1人 | 最大3人 |
| 雇用維持要件 | 5年間平均8割維持 | 未達成でも理由の報告で継続可 |
特例措置は令和9年末までの期限付きですが、要件が大幅に緩和されているため、後継者の負担を大きく軽減できる制度です。
特例事業承継税制の適用要件
特例事業承継税制の適用要件は、以下です。
先代経営者は、贈与・相続の前に同族関係者(6親等内の血族、配偶者、役員等)とともに発行済議決権株式の過半数(50%超)を保有し、かつその同族内において筆頭株主である必要があります。
例えば、取引先や従業員持株会等に株式が分散している場合、先代経営者は資金調達により株式を買い集め、50%超の持株割合を確保することが求められます。
一方、後継者は株式の贈与・相続を受けた後に、同族関係者で議決権株式の過半数(50%超)を保有する筆頭株主になることと、代表権を持つことが必要になります。
複数後継者(最大3人)を指定できる特例措置では、個々の後継者が10%以上保有し、後継者全員の合計持株割合が同族内で最大であれば要件を満たします。
参考:No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)|国税庁
特例事業承継税制の注意点
特例事業承継税制における主な注意点は、以下の通りです。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 適用期限の制限 | 2027年12月31日までの贈与・相続が対象、特例承継計画は2026年3月31日までに提出必要 |
| 継続要件期間中の制約 | 適用後5年間は代表者の継続、株式保有の維持が必須 |
| 株式譲渡の制限 | M&Aや株式売却を行うと納税猶予が取り消される |
| 継続的な報告義務 | 都道府県への年次報告書(5年間毎年)、税務署への継続届出書(3年ごと)の提出が必須 |
| 担保提供の必要性 | 猶予税額相当の担保(株式、不動産、国債等)の提供が必要 |
例えば、承継後に経営環境の変化により事業のM&Aや統合を検討する場合、株式譲渡とみなされて納税猶予が取り消される可能性があります。
また、年次報告書や継続届出書の提出を忘れた場合も、即座に猶予が取り消され、猶予されていた贈与税や相続税に加えて利子税の一括納付が必要となります。
さらに、継続要件期間中に後継者が代表者を退任した場合も、やむを得ない事情(重度の障害や介護認定等)を除き、納税猶予の取り消し事由となります。
このように、特例事業承継税制は納税猶予という大きなメリットがある一方で、長期的な株式保有と厳格な要件遵守が求められる制度です。
事業承継における株式譲渡に関するよくある質問
事業承継における株式譲渡に関してよくある質問をまとめました。
- 株式譲渡と事業承継の違いは何ですか?
- 株式譲渡で許認可は承継できますか?
- M&Aで買い手企業を見つけるまでにどの程度の期間がかかりますか?
経営者の方や、後継者として事業承継を考えている方は、ぜひこちらの情報を参考にしてください。
株式譲渡と事業承継の違いは何ですか?
事業承継とは、現在の経営者から後継者へ会社のすべてを引き継ぐことを指します。
一方、株式譲渡は経営者が持つ株式を後継者に渡すことで経営権を移転する方法です。
つまり、事業承継が「目的」で、株式譲渡が「手段」という関係になります。
事業承継では株式譲渡以外にも、生前贈与や相続といった方法があります。株式譲渡を選んだ場合、手続きが比較的簡単で、従業員や取引先との契約もそのまま引き継がれるメリットがあります。
ただし、譲渡益には税金がかかるため注意が必要です。
株式譲渡で許認可は承継できますか?
株式譲渡では基本的に許認可を引き継ぐことはできません。
なぜなら、許認可は法人に対して与えられるものであり、株式譲渡では法人格が変わってしまうためです。
事業だけを移転しても、元の会社が持っていた許認可は自動的に新しい会社に移ることはありません。
そのため、事業を受け取る側の会社は新たに許認可を取得し直す必要があります。
ただし、特例として中小企業経営強化法に基づく承継制度があります。
建設業、旅館業、一般貨物自動車運送事業、一般旅客自動車運送事業、一般ガス導管事業、火薬類製造業・販売業の6つの業種では、経営力向上計画の認定を受けることで許認可を引き継ぐことができます。
しかし、売り手と買い手のどちらかが大企業の場合は特例を使えません。
M&Aで買い手企業を見つけるまでにどの程度の期間がかかりますか?
M&Aで買い手企業を見つけるまでの期間は、一般的に半年から1年以上が目安となります。
上記は、M&Aを本格的に検討してから交渉相手が見つかるまでの準備期間であり、会社の規模や業種、希望条件によって大きく変動します。
買い手候補への匿名での打診から始まり、関心を示した企業と秘密保持契約を結び、詳細な説明や質疑応答を経てトップ面談に進むという段階的なプロセスを踏むため、これだけの期間が必要になります。
ただし、双方が迅速な進行を目指す場合は、最短2カ月で成約した事例もあります。
まとめ
事業承継における株式譲渡とは、現経営者が保有する株式を後継者へ譲り渡し、経営権を移転する最も一般的な手法です。
贈与や相続では資金負担を抑えた計画的な承継や基礎控除の活用が可能で、特例事業承継税制による税負担の軽減もあります。
特例事業承継税制の活用も検討し、専門家と相談しながら計画的に準備を進めることが重要です。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
株式譲渡による事業承継は、適切な手続きと専門的な知識が必要な複雑なプロセスです。
譲渡所得税の負担や経営支配権の移転など、様々な課題に直面する企業オーナー様も少なくありません。
一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、このような後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立された専門機関です。
JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の持続的な成長と発展を支援しています。
JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。
事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。