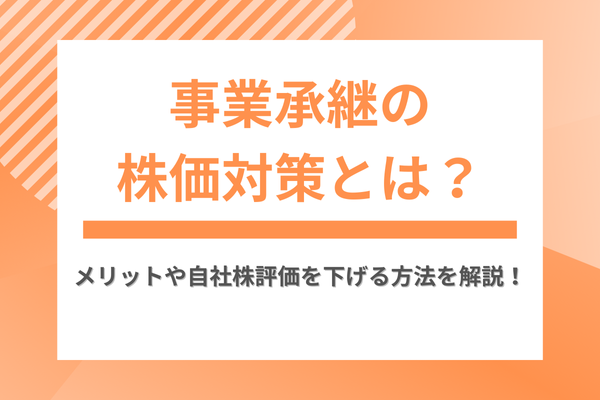「事業承継の株価対策とは?」
「事業承継における自社株価を低くする方法は?」
事業承継における株価対策とは、相続や贈与の際に発生する税負担を軽減し、後継者が円滑に会社を引き継ぐために自社株の評価額を引き下げる取り組みを指します。
株価が高いままでは、多額の相続税・贈与税や株式取得資金が必要となり、承継自体が困難になる恐れがあります。
そのため、役員退職金の支払い、不動産取得や設備投資、利益の調整など、適切な方法で株価評価を下げておくことが非常に重要です。
今回は、事業承継における株価対策の基本から、自社株を低く抑える具体的な方法、さらに実施する際の注意点までわかりやすく解説していきます。
事業承継の株価対策とは?
事業承継の株価対策とは、自社株式の評価額を引き下げて後継者にかかる相続税や贈与税の負担を抑える取り組みです。
株価が高いまま事業承継を行うと、後継者の納税負担が大きくなり、経営権のスムーズな移転や事業の存続自体が難しくなることがあります。
そのため、事前に株価対策を行うことが、円滑な事業承継に必要不可欠となります。
事業承継時における自社株の評価方法
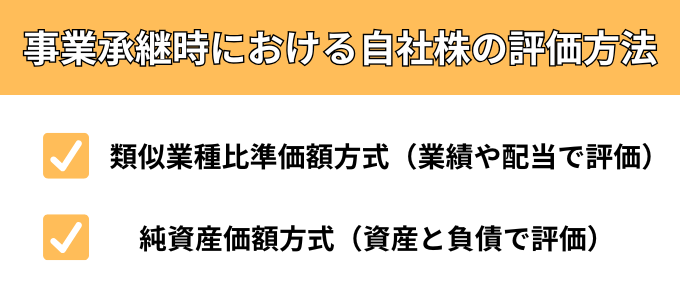
事業承継時に自社株を評価する方法には、いくつかの算定基準があります。
代表的な方式は以下の3つです。
- 類似業種比準価額方式:業績や配当を基準に評価
- 純資産価額方式:資産と負債を基準に評価
それぞれの計算方法や特徴を解説していきます。
類似業種比準価額方式(業績や配当で評価)
類似業種比準価額方式の特徴は、評価対象となる非上場企業(自社)と事業内容や規模が近い上場企業を比較し、「配当金額」「利益金額」「純資産価額」を調べて算定することです。
上記の方法ならば、主観などが入りづらく、透明性の高い評価が可能です。
類似業種比準価額方式の計算式は、以下です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 類似業種の株価 |
| 配当比準 | 自社の配当額÷類似業種の配当額 |
| 利益比準 | 自社の利益額÷類似業種の利益額 |
| 純資産比準 | 自社の純資産額÷類似業種の純資産額 |
| 斟酌率 | 大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5 |
1株あたりの株価=類似業種の株価×(配当比準+利益比準+純資産比準)÷3×斟酌率
自社の業績が高ければ評価も高くなります。
このように、類似業種比準価額方式は、業績や配当を根拠として客観的に自社株の評価が可能です。
純資産価額方式(資産と負債で評価)
純資産価額方式は、「自社を解散した場合に株主へ分配される金額」を基準に株価を評価するシンプルな方法です。
会社の資産と負債をそれぞれ時価で評価し、その差額(純資産)が自社株の価値となります。
会社の業績や将来性よりも現在の資産状況が重視されるため、計算が分かりやすいのが特徴です。
下記のように計算します。
| 項目 | 金額(万円) |
|---|---|
| 資産の相続税評価額 | 400 |
| 負債の相続税評価額 | 100 |
| 評価差額(時価−帳簿価額) | 100 |
| 法人税等相当額(評価差額×37%) | 37 |
| 純資産価額(資産−負債−法人税等相当額) | 263 |
| 発行済株式数 | 50 |
| 1株あたりの純資産価額 | 5.26 |
実際には「資産の時価−負債の時価−評価差額に対する法人税等相当額」を発行済株式数で割って求めます。
純資産価額方式は、特に中小企業の株価評価に適しており、資産と負債を時価で評価して簡便に計算できるので、事業承継時の株価算出にも取り入れやすい方法です。
事業承継する際に自社株評価を下げるメリット

事業承継における自社株評価を下げることで得られるメリットは、以下の通りです。
- 相続税・贈与税の負担を軽減できる
- 後継者の株式取得資金(買い取り・集約費用)を抑えられる
- 経営権の集中(議決権の集約)を進めやすくなる
それでは上記のメリットについて詳しく解説していきます。
相続税・贈与税の負担を軽減できる
自社株評価を下げることで、事業承継時の相続税・贈与税の負担を大きく軽減できます。
相続や贈与で事業承継する際、自社株の評価額が高いと、多額の相続税・贈与税が後継者に課されるため、株価対策は非常に重要です。
場合によっては数千万円、億単位の税金が発生することもあります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 節税効果 | 自社株評価が低くなれば、相続税・贈与税の課税額も下がります。 |
| 資金負担軽減 | 後継者が株を取得する際の費用や納税資金の準備が容易になります。 |
| 事業の安定引き継ぎ | 株式が分散しにくくなり、親族間トラブル等のリスク回避にもつながります。 |
例えば、「役員退職金を支払う」、「株式配当を低く設定する」、「不動産を購入して純資産を調整する」といった具体的な対策があります。
自社株評価を下げておくことは、相続税・贈与税の大幅な軽減につながり、後継者が安心して事業を引き継ぐためにも不可欠な対策です。
後継者の株式取得資金(買い取り・集約費用)を抑えられる
事業承継の際に「自社株評価を下げておくことで、後継者の株式取得資金(買い取り・集約費用)を抑えられる」という大きなメリットがあります。
自社株評価が高いままで後継者が株式を取得しようとすると、取得に必要な資金も多額になります。
中小企業であっても、自社株の評価額が高いと、後継者はその分多くの現金や資金を用意しなくてはいけません。
そのため、評価を低くしておくことで、実際に必要な買い取り資金や株式集約費用を減らすことができるのです。
経営権の集中(議決権の集約)を進めやすくなる
自社株評価を下げることで経営権を後継者に集約しやすくなります。
自社株の評価額が高いままだと、贈与や相続の際に多額の税金がかかり、一度に必要な分の株式を後継者へ移すハードルが上がるからです。
その結果、株式が分散しやすくなり、会社の意思決定で後継者以外の影響が強くなってしまう恐れがあります。
たとえば、会社が現経営者から自社株を買い取ることで株主数を減らし、後継者へ効率的に議決権を集約できます。
さらに、議決権の制限がある種類株式を相続人に付与し、経営に関する決定権を後継者だけが持てるようにすることも有効です。
事業承継における自社株価を低くする方法
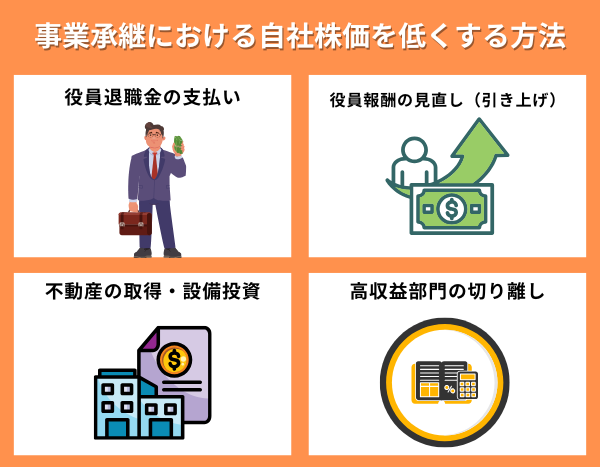
事業承継においては、相続税や贈与税の負担をできるだけ軽減するために、自社株評価を下げる工夫が欠かせません。
特に中小企業では、株価が高いままでは後継者の資金面で大きな負担となり、円滑な承継が難しくなるケースも少なくありません。
以下では、自社株価を低く抑えるために有効な方法を4つご紹介します。
- 役員退職金の支払い
- 役員報酬の見直し(引き上げ)
- 不動産の取得・設備投資
- 高収益部門の切り離し
上記の手法をうまく活用することで、税負担を抑えながらスムーズな事業承継を実現できます。
役員退職金の支払い
役員退職金の支払いは、事業承継時に自社株価を引き下げる有効な方法です。
退職金を役員に支払うことで、会社の純資産が減少します。
その結果、純資産価額方式などで計算される自社株の評価額も下がり、相続税や贈与税の負担軽減につながります。
例えば中小企業で、社長交代のタイミングで退職金を一括支給すると、会社の資産が大きく減るため、株の評価額も大きく下がります。
役員退職金の支払いは、会社の純資産を減らし、株式評価額を抑えたい方にとって有効な手段です。
役員報酬の見直し(引き上げ)
事業承継時に役員報酬を引き上げることで、自社株価を引き下げることが可能です。
自社株の評価は会社の利益や純資産を基準に算出されます。
役員退職金を支払うと会社の利益や純資産が減少し、自社株の評価額も引き下げられます。
例えばオーナー社長が退任時に適正な額の退職金を受け取ると、その金額は会社の損金として計上され、会社の純資産が減少します。
上記により事業承継時に贈与税や相続税の対象となる自社株の評価額も抑えられ、自社株の承継がしやすくなります。
円滑な事業承継だけでなく、後継者の税負担を軽減する点で大きなメリットがあります。
不動産の取得・設備投資
不動産の取得や設備投資を行うことで、事業承継時の自社株価を下げることが可能です。
自社株の評価は会社が保有する現金や内部留保が多いほど高く算定されやすいため、不動産や設備といった資産に変えることで、評価基準が変わり、結果的に株価を抑える効果が期待できるからです。
会社が多額の現金を保有している場合、そのままだと額面通りに株価に反映されてしまいます。
しかし、現金で都市部の賃貸用不動産を取得した場合、不動産は路線価や固定資産税評価額で評価されるため、現金よりも評価が下がるケースが多いです。
また、新たな設備投資を行うことで減価償却が進み、会計上の利益が圧縮され、株価引き下げることができます。
高収益部門の切り離し
事業承継時に自社株価を低く抑えるためには「高収益部門の切り離し」が非常に有効です。
高収益部門が会社の利益を大きく押し上げていると、その分、株価評価も高くなり、後継者が相続や贈与の際に多額の税負担を負います。
回避するために、高収益部門を切り離すことで本体の利益を圧縮し、自社株の価値を下げることが可能です。
| 手法 | 詳細 | 後継者の影響 |
|---|---|---|
| 分社型分割 | 高収益部門を新設した子会社へ移転 | 子会社の株式取得などで事業引継可 |
| 事業譲渡 | 高収益部門を後継者の新会社に譲渡 | 新会社で高収益部門を経営が可能 |
但し、分割や譲渡の方式によっては税務上の注意点もあるため、事前に専門家へ相談することが重要です。
事業承継で自社株の評価額を下げる際の注意点
事業承継を進める際には、自社株の評価額を引き下げる方法を検討することがあります。
しかし、株価を下げて後継者への承継を行う場合には、税務や法務の面で多くの注意点が存在します。
自社株評価額を引き下げる際の主なリスクは次の3つです。
- 低額譲渡は「みなし贈与」課税になり得る
- 自己株式取得(金庫株)には税務・法務の制約がある
- 実態に沿わない「株価下げ目的のみ」の施策は否認される
誤った方法で実施すると、かえって大きな税負担やリスクを抱えることにつながってしまいます。
低額譲渡は「みなし贈与」課税になり得る
低額譲渡は「みなし贈与」として贈与税が課税される可能性があります。
仮に家族や後継者のための事業承継であっても、時価よりも著しく低い金額で自社株などを譲渡した場合、実質的に経済的利益を贈与したとみなされてしまうためです。
税務上は、贈与の意思がなくても、時価と譲渡価額の差額を贈与と判断します。
自社株の時価が1,000万円なのに、譲渡価額を400万円に設定して息子に譲渡したとしましょう。この場合、差額の600万円が「みなし贈与」となり、受け取った側に贈与税が課税されます。譲渡者側には、譲渡価額から取得費を引いた分の譲渡益課税も発生します。
このように、事業承継で自社株の評価額を下げて後継者へ低額譲渡すると、「みなし贈与」課税という大きなリスクが伴います。
自己株式取得(金庫株)には税務・法務の制約がある
自己株式取得(金庫株)を活用して事業承継時に自社株評価額を引き下げようとする場合、税務・法務両面で厳しい制約があるため慎重な対応が必要です。
自己株式取得には、会社法で定められた手続きや財源規制があるほか、税務上も「みなし配当」や「みなし譲渡」など独自の課税ルールが適用されます。
| 主な制約 | 内容 |
|---|---|
| 税務(みなし配当課税) | 譲渡価額のうち資本金超部分は配当所得として課税 |
| 税務(みなし譲渡課税) | 不当に安い価格の場合は時価で譲渡したとみなされ課税 |
| 法務(財源規制) | 分配可能額を超える自己株式取得はできない |
| 法務(手続き) | 株主総会・取締役会の決議や債権者保護手続などが必要 |
上記を無視すると、想定外の税負担や手続きミスが発生し、かえってコストやリスクが増す場合があります。
実態に沿わない「株価下げ目的のみ」の施策は否認される
実態に合わない、単に株価を下げるだけの施策は、税務署に否認され追加課税される恐れがあるので注意しましょう。
株価を不当に下げる行為は「租税回避行為」と判断される可能性があります。
税金負担を軽減する目的のみで実態が伴わない場合、税務署はその行為を認めず、後から多額の税金を請求される場合があります。
| 施策例 | 注意点 |
|---|---|
| 持株会社を設立 | 株価対策で使われがちだが、税金逃れ目的とみなされるケースも。実質的な経営改善等の実態が必須 |
| 高額な役員報酬 | 利益圧縮で株価低下を狙っても、不相当に高い部分は否認対象 |
| 配当をゼロに設定 | 評価額下げの意図だけの場合は否認される恐れ |
株価下げの施策は、実際の事業活動や経営改善策と整合性がある必要があります。
事業承継の株価対策に関するよくある質問
最後に、事業承継における株価対策について、よくある質問とその回答をまとめます。
- 事業承継で株価を下げる対策を実行するタイミングはいつが最適ですか?
- 株価対策を一切行わない場合はどのようなリスクが生じますか?
- 株価対策として不動産を購入する場合はどのような物件を選べばいいですか?
- 事業承継で株価を下げる対策を実行するタイミングはいつが最適ですか?
-
事業承継で株価を下げる対策は、承継直前期末までに実施するのが最適です。
- 役員退職金の支給や役員報酬の引き上げを決算期末前に実行する
- 不動産や有価証券の売却などで純資産を減らす対策を、直前期末までに終えておく
- 一時的な利益圧縮策を決算期に合わせて行う
株価の評価基準日は、事業承継や相続が発生した時点やその期末となるため、その時点での自社株価が相続税や贈与税の計算に反映されます。
したがって、直前期末までに株価を下げる対策を講じておくことで、税負担の軽減につながります。
- 株価対策を一切行わない場合はどのようなリスクが生じますか?
-
株価が高いまま事業承継をすると、後継者の相続税・贈与税負担が過大になったり、経営権移転や遺産分割が円滑に進まず、会社経営に深刻な悪影響を及ぼす可能性が高くなります。
リスク 具体例 過大な税負担 後継者が納税資金を用意できず、会社資産や自社株を売却せざるを得なくなる。 経営権の分散 株式が分散し、意思決定が遅れ、会社の方針がまとまらなくなる。 遺産分割トラブル 高評価の株が分割困難となり、「争族」が発生するリスクが高まる。 財務基盤への悪影響 株主が増えることで会社の自由度が下がり、持続的成長への支障となる。 事業承継で株価対策を怠れば、納税負担・経営権・円滑な継承の全てにリスクが及ぶため、事前の計画的な対策が不可欠です。
- 株価対策として不動産を購入する場合はどのような物件を選べばいいですか?
-
株価対策として不動産を購入する際は、賃貸用不動産(アパート・賃貸マンション・貸事務所や貸店舗など)を選び、取得から3年以上経過させておくことが重要です。
賃貸用不動産は、相続税評価や株価評価の際に「路線価」や「固定資産税評価額」「借家権割合」などが適用されるため、実際の時価よりも低い評価額になりやすいからです。
現金で保有しているよりも資産評価額を圧縮でき、結果的に純資産額や株価が下がります。
まとめ
事業承継の株価対策とは、自社株の評価を下げることで相続税・贈与税や後継者の資金負担を軽減し、円滑な事業承継を実現するための重要な取り組みです。
役員退職金の支払い、不動産取得、高収益部門の切り離しなどを組み合わせることで、効果的に株価を下げることができます。
ただし、みなし贈与課税や租税回避行為の否認リスクなどの注意点も存在するため、専門家の助言を得ながら進めることが欠かせません。
今回のポイントを踏まえて、読者の皆さまには 「早めに株価対策を計画し、税務・法務リスクを避けながら後継者の負担を最小限に抑える準備」 を実行していただきたいと思います。
株価対策を怠ると、多額の税負担や経営権分散など、事業存続に大きな支障をきたす可能性があります。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
事業承継や株価対策は、会社や業界ごとに最適な方法が異なり、税務・法務面での複雑なリスクも伴います。
円滑な承継を進めるためには、専門的知見をもつパートナーの存在が不可欠です。
日本プロ経営者協会は、国内最大級のプロ経営者ネットワークを活用し、中小企業からクリニック・医院まで、幅広い事業承継課題に対応してきた実績があります。
親族内承継から第三者承継(M&A)まで柔軟にサポートし、経営統合・承継後の運営方針策定まで一貫して支援が可能です。
後継者問題や事業承継でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。