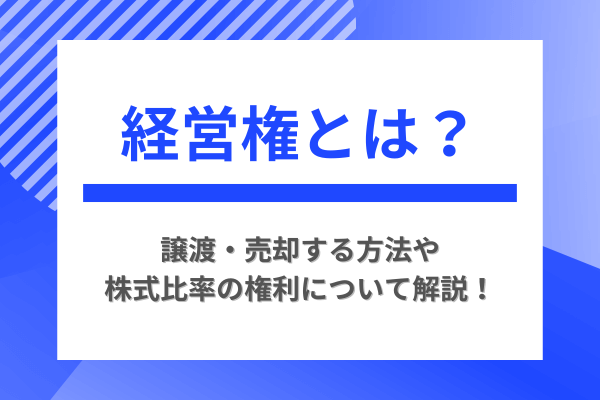「経営権とは何か?」
「経営権を譲渡するにはどうすればよいのか?」
経営権とは会社を経営する権利のことで、実際には株主が保有する重要な権利です。
発行済株式の過半数を所有していれば経営権があるとみなされ、取締役の選任・解任や役員報酬の決定などが可能になります。
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 会社分割
本記事では、「経営権の基本概念」や「経営権を譲渡する方法」について詳しく解説していきます。
事業承継やM&Aを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
監修者

代表理事
小野 俊法
経歴
慶應義塾大学 経済学部 卒業
一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。
その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。
その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。
投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。
経営権とは
経営権とは、会社の経営方針や役員の人事、利益の分配などを実質的に決められる「経営の主導権」です。
実際に経営を動かすのは社長や役員ですが、根本的な決定権を持つのは株式を保有する株主です。
特に議決権のある株式を過半数(50%超)持つ株主は、株主総会で普通決議を単独で通すことができ、取締役の選任や解任、役員報酬の決定などを自由に行えます。
例えば、発行済株式の51%を保有していれば経営権を握り、66.7%以上を持てば定款変更や合併など特別決議も単独で成立させられます。
つまり、経営権を持つということは、会社の「舵」を握るということです。
事業承継やM&Aを考える中小企業の経営者にとって、経営権の仕組みを理解することは、自社の未来を守るうえで欠かせない要素です。

経営権と支配権の違いとは?
経営権は企業の日常的な経営を行う権利であり、支配権は企業の重要事項を決定する権利です。
| 項目 | 経営権 | 支配権 |
|---|---|---|
| 必要な株式保有比率 | 過半数(50%超) | 3分の2以上(約66.7%) |
| 決議の種類 | 普通決議 | 特別決議 |
| 主な権限 | 取締役選任・解任 役員報酬決定 | 定款変更 M&A 株式併合 |
| 対象事項 | 日常的な経営事項 | 会社の根本的変更事項 |
経営権は議決権のある株式の過半数(50%超)を保有することで獲得でき、株主総会の普通決議を可決させる権限です。
経営権を持つことで、取締役の選任・解任、役員報酬の決定、利益処分案の決定などが可能になります。
真の意味での経営権は、経営者を選任できる権利を持つ株主が保有しています。
支配権は議決権のある株式の3分の2以上を保有することで獲得でき、株主総会の特別決議を可決させる権限です。
支配権により定款変更、合併・会社分割などのM&A、株式併合などの重要事項を決定できます。
経営権と経営三権の違いとは?
経営権は株主や経営者が企業全体の意思決定を行う「経営に関する権利」であり、経営三権は経営者が労働者に対して持つ「現場の管理に関する権利」です。
| 項目 | 経営権 | 経営三権 |
|---|---|---|
| 権利を持つ主体 | 株主・経営者 | 経営者(使用者) |
| 内容 | 会社全体の方針や経営判断を行う権利 | 労働者に対して業務を指示・管理する権利 |
| 主な権限 | 経営方針の決定、取締役の選任・解任など | 業務命令権 人事権 施設管理権 |
| 対象 | 会社全体や経営活動 | 職場・従業員の管理運営 |
たとえば、ある企業で社長が従業員に業務を指示し、配置転換を行うのは経営三権のうち「業務命令権」「人事権」の行使です。
しかし、社長を選任したり経営方針を決めたりするのは、株主が持つ経営権によるものです。
つまり、株主が経営権を握ることで、どの経営者が三権を行使できるかが決まります。
このように、経営権が「会社の大きな舵取りを決める権利」なのに対し、経営三権は「その舵を現場で動かす権利」です。
会社の経営権と支配権のために必要な株式の割合
会社の経営権を得るには過半数(50%超)、支配権を得るには3分の2以上(約66.7%)の株式が必要です。
| 権限の種類 | 必要な株式保有比率 | 可能な決議内容 |
|---|---|---|
| 経営権 | 50%超 | 取締役・監査役の選任、役員報酬、配当決定など |
| 支配権 | 約66.7%以上 | 定款変更、合併・会社分割などの承認 |
| 拒否権 | 33.4%以上 | 特別決議の阻止が可能 |
上記は、会社法における株主総会での決議基準に基づいています。
50%超の株式を持つと「普通決議」が単独で通せるため、経営者の選任や役員報酬の決定などができます。
一方、3分の2以上の株式を持つと「特別決議」が可能となり、定款変更や合併・株式併合など、会社の根本に関わる事項を決定できます。
このように、経営権を得たいなら50%超、会社のすべてを動かす支配権を得たいなら3分の2以上の株式取得を目指すことが大切です。
経営権の譲渡とは
経営権の譲渡とは、会社の経営権を第三者に譲り渡すことです。
株式会社では、真の経営権保持者は株主であるため、経営権の譲渡は主に株式譲渡によって実現されます。
過半数以上の株式を譲渡することで、買い手は普通決議での決定権を獲得し、実質的な経営権を得ることができます。
事例として、中小企業の後継者不足問題で悩む経営者が、M&Aによって会社の全株式を他社に譲渡するケースがあります。
また、不採算部門を切り離したい場合には、事業譲渡という手法で特定事業のみを譲渡することも可能です。
株式譲渡では会社がそのまま存続するため、手続きが簡単であるというメリットがあります。
経営権を譲渡する3つの方法

経営権を譲渡する方法は、以下の3つです。
| 方法 | 特徴 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 中小企業のM&Aで多く採用されている | 会社全体 |
| 事業譲渡 | 譲渡範囲を自由に選択 | 選択した事業のみ |
| 会社分割 | 資産・負債が自動承継 | 分割対象事業 |
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
株式譲渡
株式譲渡は会社の議決権を持つ株式を買い手に売却することで、経営権を直接移転させる手法です。
中小企業のM&Aの約90%が株式譲渡で実施されており、手続きが簡単で法的にも確実性が高いことが特徴となります。
まず株式譲渡承認請求書を会社に提出し、取締役会での承認を得ます。
その後、買い手と株式譲渡契約を締結し、株主名簿の書き換えを行うことで経営権が正式に移転されます。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を第三者に売却・移転するM&A手法です。
株式譲渡では会社全体の経営権が移転しますが、事業譲渡では譲渡したい事業の範囲を自由に選択できます。
また、売り手企業は事業の資産・負債・従業員を個別に選択して譲渡できるため、リスクを限定しつつ経営権を移転することが可能です。
例えば、製造業の会社が複数の事業部門を持つ場合、不採算部門だけを切り離して譲渡することで、その部門の経営権のみを買い手に移転できます。
手続きとしては、取締役会決議から始まり、事業譲渡契約の締結、株主総会での特別決議を経て完了します。
商品・設備・従業員・取引先との関係なども含めた事業全体が譲渡対象となるため、実質的な経営権の移転が実現されます。
会社分割
会社分割とは、株式会社が事業上の権利義務の全部または一部を分割して、他の会社に承継させるM&A手法の一つです。
通常の売買取引とは異なり、分割した事業に関わる資産、負債、契約、従業員などが自動的に承継会社に引き継がれます。
会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2つの方法があります。
吸収分割は既存の会社に事業を承継させる方法で、新設分割は新たに設立する会社に事業を承継させる方法です。
また、分割の対価を誰が受け取るかにより、分社型と分割型に分けられます。
例えば、自社の一部事業を既存の会社に譲渡したい場合は「吸収分割」を選択し、対価として承継会社の株式を受け取ることで、承継会社との資本関係を構築できます。

経営権を確保する方法
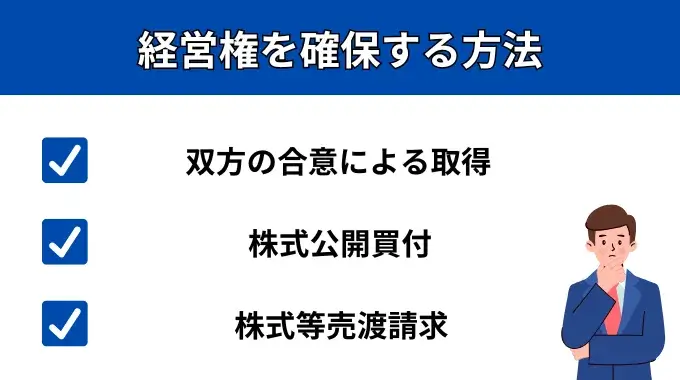
経営権を確保する方法は以下の通りです。
- 双方の合意による取得
- 株式公開買付
- 株式等売渡請求
経営権の確保には複数の手法があり、それぞれ異なる状況や目的に応じて使い分けることが重要です。
それでは上記の方法について解説していきます。
双方の合意による取得
経営権を確実に得たい場合、双方の合意による株式取得は最も現実的かつ安全な手段です。
双方の合意に基づいた取得であれば、相手株主との信頼関係やトラブル回避が期待できます。
加えて、一定の議決権比率以上の株式を取得することで、経営方針の決定や取締役選任など重要な経営権限を行使できるようになります。
例えば、ある会社の経営権取得を目指す場合、主要株主と合意し過半数以上の株式を取得できれば、取締役の選任・解任など会社の方向性を自分の意向で決めることができるようになります。
株式公開買付
株式公開買付は市場外で多くの株主から株を直接買い取ることで、短期間で企業支配権を得るための方法です。
TOBとは、「株式公開買い付け(Take Over Bid)」の略称で、買収の手法として用いられる。通常の市場売買ではなく、事前に買い取る期間や株数、買付価格の情報を不特定多数の株主に対して広く提示し、市場外で買い付けることを指す。
TOBでは買付価格や期間を事前に公告し、不特定多数の株主から効率よく株式を取得できます。
買収企業が相手企業の発行済株式50%以上をTOBで取得すれば、取締役の選任や経営方針の決定など、企業の経営権を独占的に握ることができます。
さらに、2/3以上を取得すれば、合併や事業売却といった特別決議も単独で成立させることが可能です。
以下の表は持株比率と得られる経営権の目安を示しています。
ただし、買付価格にプレミアムが必要となるため、コスト面のリスクも理解した上で慎重に進めることが大切です。
株式等売渡請求
株式等売渡請求は、経営権を安定的に確保したい経営者にとって有効な制度です。
具体例として、A社の経営者が90%の株式を保有し、残り10%を外部株主が持っていた場合を考えます。
外部株主が取締役の選任や企業再編に反対した際、株式等売渡請求を行うことで全株式を取得し、経営権を確保することが可能です。
この手続きは、対象会社への通知・承認・公告という流れで進み、20日前に少数株主へ通知するルールが定められています。
このように、株式等売渡請求は経営の停滞を防ぎ、事業承継やM&Aの場面でも活用できる方法です。
最終的に、経営権を守りたい経営者にとって、会社の将来を安定的に運営するための重要な手段になるといえます。
経営権の譲渡で起こりやすい問題
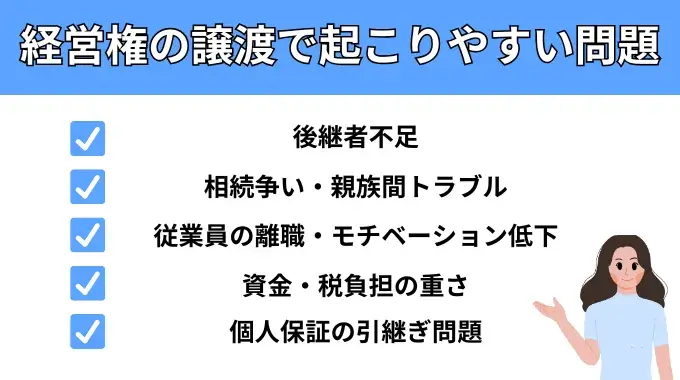
経営権の譲渡で起こりやすい問題は、以下の通りです。
- 後継者不足
- 相続争い・親族間トラブル
- 従業員の離職・モチベーション低下
- 資金・税負担の重さ
- 個人保証の引継ぎ問題
経営権の譲渡は、ただ事業を引き継ぐだけではなく、企業そのものの未来に大きな影響を与える重大なプロセスです。
準備や対応が不十分だと、会社の存続が危ぶまれたり、親族や従業員との関係に深刻な亀裂を生むこともあります。
問題がこじれる前に、正しい知識と冷静な判断を持ち、関係者との信頼関係を築きながら進めることが大切です。
後継者不足
経営権の譲渡における「後継者不足」は、企業存続に大きな問題を引き起こしています。
少子化やライフスタイルの多様化によって、親族や従業員で経営を引き継ぐ人材が見つからないケースが増えているためです。
例えば、近年では親世代も「子どもに無理に事業を継がせたくない」と考える傾向が強まっています。
また、経営者としての能力や想いの継承、さらには経営スキルや業界知識が求められる点もハードルとなっています。
業績が良くても後継者不足で事業が継続できない現実は、他にも多くの中小企業が直面しています。
相続争い・親族間トラブル
経営権の譲渡では、親族間での対立や感情的なもつれから深刻なトラブルが発生しやすいです。
経営権は会社の実権そのものであり、相続人それぞれが自分の正当性や期待を抱いているため、株式や役職の分配方法によって不満が生じやすいです。
たとえば、創業者が急逝し後継者指定が曖昧だった場合、兄弟間で「自分こそが後継者」と主張して争いに発展し、話し合いが決裂して会社が分裂するケースがあります。
また、株式を複数の親族で分けてしまうと、重要な決定ができなくなり、会社経営が立ち行かなくなることもあります。
最悪、裁判や社外株主を巻き込む泥沼の争いに発展し、会社の存続自体が危ぶまれます。
従業員の離職・モチベーション低下
経営権の譲渡時には、従業員の離職やモチベーション低下が発生しやすくなります。
主に雇用条件や職場環境の変化、会社方針の違いによる「不安」や「将来への不透明感」が従業員に広がるためです。
例えば事業譲渡の場合、新たな雇用契約の締結や待遇の見直しが行われるケースが多く、給与や勤務地、役職、福利厚生といった身近な働き方が変わることがあります。
このような変化は従業員にとって大きなストレスとなり、「今後この会社で働き続ける価値があるのか」と疑問を感じやすくなるのです。
資金・税負担の重さ
経営権の譲渡を検討する際、資金調達の難しさと税負担の重さが大きな障壁となります。
特に中小企業の経営者にとって、事業承継やM&Aを諦める原因にもなりかねません。
経営権譲渡では、譲渡する側に多額の税金が課されます。
個人が株式譲渡を行う場合、譲渡所得に対して所得税・住民税合わせて20.315%の税率が適用されるのです。
たとえば、譲渡益が1億円の場合、約2,031万円の納税が必要となり、現金での納税資金確保が求められます。
一方、事業譲渡の場合は譲渡益に対して約30〜34%の法人税等が課税され、さらに消費税の納税義務も発生するため、税負担はより重くなります。
対策
| 対策 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 事業承継税制の活用 | 相続税・贈与税が最大100%免除される | 適用条件が厳しく、雇用維持などの要件がある |
| 株式譲渡の選択 | 税率20.315%と事業譲渡より低い | 譲渡益が大きい場合、納税額も高額になる |
| 金融機関からの融資 | 自己資金不足を補える | 中小企業は審査通過が困難で、のれん代への融資は特に難しい |
このように、経営権譲渡における資金・税負担の問題は、売り手・買い手の双方に深刻な影響を及ぼします。
専門家へ相談し、事業承継税制などの支援制度を活用することが大切です。
個人保証の引継ぎ問題
経営権を譲渡しても個人保証が自動的に解除されないため、旧経営者が多額の債務を背負い続ける危険があります。
中小企業では、金融機関からの融資時に経営者個人の保証が求められるのが一般的です。
しかし、会社を売却しても保証の名義変更は自動で行われません。
新経営者が保証契約を引き継ぐには、金融機関の同意が必要となります。
交渉が不十分だと、旧経営者だけが責任を負う事例も発生しています。
このように、経営権を譲渡する際は、個人保証の扱いを軽視してはいけません。
専門家や金融機関と連携し、保証解除の手続きを確実に進めることで、安全に経営を引き継ぐことができます。
経営権に関するよくある質問
会社経営や株式保有に関して、多くの方が疑問に思う「経営権」についてのよくある質問を紹介します。
- 経営権を握るには株式を何パーセント保有する必要がありますか?
- 社長と株主はどちらの方が会社での立場が上ですか?
- 個人事業主に経営権という概念は適用されますか?
- 経営権を持たない取締役はどのような役割や制限がありますか?
- 経営権の譲渡価格の相場はどのように決まりますか?
上記の疑問をわかりやすく解説していますので、気になる方はぜひチェックしてください。
経営権を握るには株式を何パーセント保有する必要がありますか?
経営権を握るには、会社の発行済株式の過半数(50%超)を保有する必要があります。
過半数の議決権があれば、株主総会における普通決議(取締役・監査役の選任や役員報酬の決定など)を単独で可決できるからです。
| 保有割合 | 行使できる権利 |
|---|---|
| 33.4%以上 | 特別決議の否決権 |
| 50%超 | 普通決議の可決(経営権) |
| 66.7%以上 | 特別決議の単独可決 |
- 株式総数が100株の場合は、51株以上を保有すれば経営権を握れます。
- 共同創業者が複数いるケースでも、1人が51%以上を持っていれば単独で重要事項を決定できます。
社長と株主はどちらの方が会社での立場が上ですか?
会社で「立場が上」なのは株主です。
| 立場 | 権限・役割 |
|---|---|
| 株主 | 会社の所有者。取締役・社長の選任・解任ができる。会社の重要事項を最終決定。 |
| 社長 | 会社を代表して経営実務を担う。ただし就任・退任は株主の決議次第である。 |
株主は会社の所有者であり、株主総会で社長(取締役)を選任・解任する権限を持っています。
例えば、オーナー社長の場合、社長自身が株式を多数保有していれば、経営判断を自分の意思で自由に行えます。
しかし、雇われ社長の場合は、株主が別にいて、その判断に従わなければなりません。
個人事業主に経営権という概念は適用されますか?
個人事業主にも「経営権」という概念は適用されます。
法人の場合は経営権が株主の持つ株式に基づいて存在しますが、個人事業主の場合は、事業を経営する権利や事業にまつわる財産など全てが事業主個人に属しています。
そのため、経営権も事業主1人に帰属します。
経営権を持たない取締役はどのような役割や制限がありますか?
代表権や経営権を持たない取締役は、会社を法的に代表することはできませんが、経営方針の助言や業務監督といった重要な役割を担います。
会社法では、代表取締役のみが法人を対外的に代表できると定めており、他の取締役はその行為を行えません。
ただし、経営の質を高めるために助言や監視機能を果たすなど、経営の健全性を支える責任があります。
| 区分 | 代表権の有無 | 主な役割 | 制限される行為 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役 | あり | 契約・押印・対外業務代表 | 特になし |
| 代表権のない取締役 | なし | 経営監督・助言・意思決定支援 | 契約締結・押印・訴訟対応 |
このように、経営権を持たない取締役は、表に出るよりも内部統制を支える立場です。
直接業務を行うよりも、経営判断を監督・助言する役割に重点が置かれます。
経営権の譲渡価格の相場はどのように決まりますか?
経営権の譲渡価格には明確な相場がなく、最終的には買い手と売り手の交渉によって決まります。
企業の財務状況や将来性、ブランド力などによって価値が大きく変動するため、一律の基準は存在しません。
譲渡価格を決める際は「企業価値評価(バリュエーション)」という考え方を用います。
一般的に「純資産+営業利益×数年分」で算出する年倍法(利益年倍法)が目安とされ、過去の利益をもとに将来の収益性を評価します。
また、ブランドや技術力、ノウハウなどの無形資産(のれん)も価格に影響します。
たとえば純資産が1,000万円、年間営業利益が300万円の企業なら、年倍法で「1,000万円+(300万円×3~5年)」となり、相場は1,900万~2,500万円程度が目安となります。ただし、業種や経済状況によって3年分より低くなることも高くなることもあります。
まとめ
経営権とは、会社を経営する権利であり、実質的には株主が保有しています。
株式を過半数以上持つことで普通決議を通せる「経営権」を、3分の2以上持つことで特別決議を通せる「支配権」を獲得できます。
また、経営権の譲渡は主に「株式譲渡」「事業譲渡」「会社分割」という3つの方法があり、中小企業M&Aでは株式譲渡が最も一般的です。
経営権を理解することは、経営者はもちろん、株主や事業承継を検討している方にとって重要です。
自社の株式保有割合や、今後の承継・譲渡の方法についてあらかじめ整理し、専門家に相談しながら計画的に進めていくことをおすすめします。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
経営権の譲渡や事業承継は、単なる株式の売却やM&Aにとどまらず、会社の未来全体に関わる重大な意思決定です。
特に中小企業では、後継者不足や親族内での調整が難航し、存続そのものを揺るがす事態も少なくありません。
日本プロ経営者協会は、国内最大級のプロ経営者ネットワークを活用し、様々な事業承継・経営統合に豊富な実績を持っています。
複雑な承継スキームの設計から、承継後の経営戦略策定まで一貫してサポートいたします。後継者問題や経営権の譲渡でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。