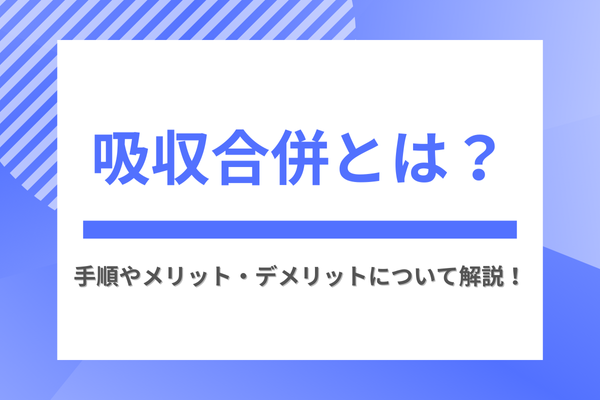「吸収合併とは?」
「吸収合併のメリットはなに?」
企業経営やM&Aに関心のある方なら、こうした疑問を持ったことがあるのではないでしょうか。
吸収合併とは、一方の会社がもう一方を取り込み、消滅した会社の資産・権利・義務をすべて存続会社が引き継ぐ仕組みです。
- 権利義務を一括で引き継げる
- シナジーを早期に実現しやすい
- 対価設計の柔軟性(資金負担の軽減)
経営資源を効率的に統合し、事業規模の拡大やシナジー効果を早期で狙える点が大きな特徴となります。
また、契約や許認可を改めて取り直す必要がないため、手続きを簡素化でき、対価設計の柔軟性によって資金負担を軽減できるのも魅力です。
一方で、手続きの負担や株主比率への影響など注意点も存在します。
今回は、「吸収合併の基本的な仕組み」や「手続きの流れとスケジュール」などについて詳しく解説していきます。
これから吸収合併を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
吸収合併とは?
吸収合併とは一方の会社がもう一方を取り込み、消滅した会社の権利や義務、資産を残った会社がすべて引き継ぐ手続きです。
事業の拡大や効率化を目指して使われることが多く、複数の会社をまとめることで競争力を高めたり、コスト削減を図ったりするために活用されます。
例えば、A社とB社があり、A社がB社を吸収合併した場合、B社は解散し法人格がなくなります。
B社が保有していた工場や店舗、従業員、契約などすべてがA社へと移ります。
事業やお金、責任もA社に統合されます。一般的に大きな会社が小さな会社を吸収する形が多いです。
吸収合併を行う目的
吸収合併を行う最大の目的は、経営の効率化やシナジー効果の獲得、事業規模の拡大です。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 経営の効率化 | 組織・業務の一本化、コスト削減 |
| シナジー効果の創出 | 技術・人材の掛け合わせで新たな価値 |
| 市場シェア・事業規模の拡大 | 経営資源を統合し競争力向上 |
| 意思決定の迅速化 | 統合によるマネジメント強化 |
| 資産・負債の承継 | 複雑な資産移転手続きを省略 |
例えば、親会社が子会社を吸収合併した場合には、今まで別々だった管理部門などを一体化し、コスト削減や業務効率化が実現できます。
また、異なる分野のノウハウや技術を持つ企業が統合されれば、新たな商品やサービスの開発も期待できます。
吸収合併は、複雑な手続きやコストが発生する面はあるものの、会社経営の方向性で悩む方には事業の将来性や効率化、成長加速のための有効な手段です。
吸収合併と新設合併の違い
吸収合併と新設合併の大きな違いは、「存続する会社があるかどうか」です。
吸収合併ではどちらか一方の会社が存続しますが、新設合併では関係する全ての会社が消滅し、新たに新会社が設立されます。
| 項目 | 吸収合併 | 新設合併 |
|---|---|---|
| 存続会社 | 既存会社が存続 | 全社が消滅し新会社を設立 |
| 権利・義務の承継 | 存続会社が引き継ぐ | 新会社が全て引き継ぐ |
| 許認可の扱い | 引き継げる | 再取得が必要 |
| 上場の維持 | 存続会社のまま維持しやすい | 新会社なので新規上場手続きが必要 |
| 株主への対価 | 株式・社債・現金も可能 | 原則、株式や社債(現金は不可) |
承継される権利義務や手続き、対価の内容、許認可の承継可否などが異なります。
たとえば、吸収合併では既存の会社のままなので手続きを簡単に済ませやすい一方、新設合併では新会社になるため各種許認可や上場手続きなどが再度必要になるケースが多くなります。
吸収合併の3つのメリット

吸収合併のメリットは、次の3つです。
- 権利義務を一括で引き継げる
- シナジーを早期に実現しやすい
- 対価設計の柔軟性(資金負担の軽減)がある
吸収合併には、手続きやコストを抑えつつ、事業や資源の統合をスピーディーに進められるといった特徴があります。
それでは、上記のメリットについて解説していきます。
権利義務を一括で引き継げる
吸収合併の最大のメリットは「権利義務を一括で引き継げる」ことです。
例えば、A社がB社を吸収合併する場合、B社が持っていた複数の契約や特許、承認済みの許認可は、手続きをせずに全てA社にまとめて移ります。
そのため合併後も取引や事業運営がスムーズに継続でき、関係者との個別交渉や再申請の負担がなくなります。
このように、吸収合併は「権利義務を一括承継できる」ことで、特に手続きを簡素化したい人や、すぐに事業を引き継いで再スタートしたい人には大きなメリットです。
シナジーを早期に実現しやすい
吸収合併は、シナジーを早期に実現しやすいことが大きなメリットです。
吸収合併によって複数の会社が1つの法人格となり、経営資源やノウハウ、人材や技術などを即座に統合できるからです。
個別の契約変更や別会社としての調整が必要なく、合併後すぐに一体運営が始まります。
ソフトバンクと日本テレコムの合併では、インフラの統合や経費削減などシナジーが短期間で実現され、企業価値の向上につながっています。
このように、吸収合併は経営資源を一体化できるため、シナジー効果を素早く発揮しやすい手法といえます。
対価設計の柔軟性(資金負担の軽減)
吸収合併では「対価設計の柔軟性」により、資金負担を大きく軽減できるメリットがあります。
吸収合併では合併で消滅する会社の株主に対して「株式」「社債」「現金」など多様な形で対価を支払えるためです。
この柔軟性によって、存続会社は手元資金を大きく減らすことなく合併を成立させることができ、資金調達コストや負担感を抑えることが可能です。
現金だけで対価を支払う必要はありませんので、企業のキャッシュフローを守りながらM&Aを進められます。
吸収合併の3つのデメリット
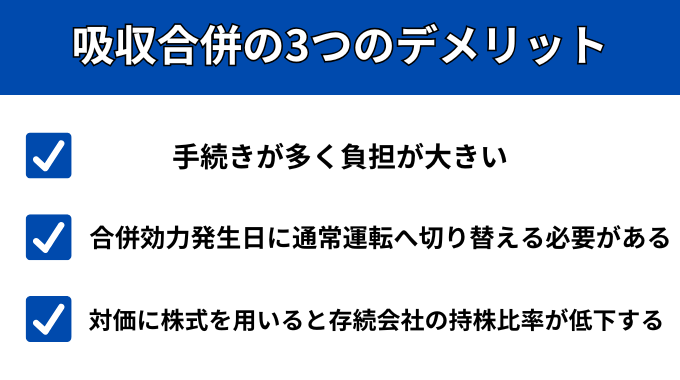
吸収合併を検討する際に、あらかじめ知っておくべき3つのデメリットは、以下のとおりです。
- 手続きが多く負担が大きい
- 合併効力発生日に通常運転へ切り替える必要がある
- 対価に株式を用いると存続会社の持株比率が低下する
吸収合併は、経営資源の統合やシナジー効果が期待できる一方で、実務の負担や株主構成の変化など、見過ごせないリスクも存在します。
特に、効力発生日が近づくと現場の対応に大きなプレッシャーがかかり、事前準備不足が原因で混乱が生じるケースも少なくありません。
上記のポイントを理解しておくことで、リスクを最小限に抑え、スムーズな吸収合併につながります。
手続きが多く負担が大きい
吸収合併は手続きが多く、現場や関係者に大きな負担がかかる点がデメリットです。
吸収合併では、会社法に基づくさまざまな手続きが求められます。
たとえば、株主総会の特別決議や債権者保護手続き、契約書作成・公告など多岐にわたり、単なる株式譲渡に比べて手続きが格段に増えます。
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 吸収合併契約書の作成 | 何度も内容確認や調整が必要 |
| 株主総会の招集・開催・特別決議 | 日程調整や議論、決議など負担が大きい |
| 債権者保護手続き、公告 | 官報掲載や関係各所への通知が必要 |
| 統合作業(システムや組織の統合) | 効力発生日までに完了しないと通常業務に影響 |
| 反対株主や取引先への対応 | 複雑かつ多岐にわたる調整が発生 |
現場では普段の業務に加え、これら統合作業を短期間でこなす必要があるため、疲弊や混乱のリスクも高まります。
吸収合併はメリットも多い一方、手続きが多く現場の負担が大きいことに悩むケースが多いです。
合併効力発生日に通常運転へ切り替える必要がある
吸収合併を行う場合、効力発生日にあわせて通常運転に切り替える必要があります。
合併効力発生日とは、合併契約書で定められた「法的に合併の効力が発生する日」のことです。
この日になると、消滅会社の権利や義務が存続会社に一括して承継され、消滅会社は法律上解散したものと見なされます。効力発生日時点では、株主の権利移動や許認可の承継といった関連手続きも同時に発生します。
特に効力発生日は、双方の企業管理・業務・システム統合作業をこの日に間違いなく完了させなければいけません。
猶予なく一斉に運用を一社にまとめることで、混乱や業務停滞の危険が高まります。
現場にはプレッシャーがかかり、システム移行の失敗や、現金精算のトラブルも発生しやすくなります。
事前の準備が不足していると取引先や顧客、従業員に大きな混乱を招いてしまいます。
対価に株式を用いると存続会社の持株比率が低下する
対価に株式を用いると、存続会社の持株比率が低下します。
吸収合併において存続会社が消滅会社の株主に対し自社の株式を交付するため、存続会社の既存株主が保有していた比率が希薄化してしまうからです。
現金を用いないため資金調達の負担は軽減できますが、その分株式が新たに分配されることになります。
存続会社Aが消滅会社Bを吸収合併する際、Bから移ってきた株主に対しAの株式を発行します。
例えば、Aの株主が100株、Bの株主が50株分(合併比率による割当後)を受け取る場合、合併後Aの株数は150株となり、元々のA株主の持株比率は100/150=約66.7%へ低下します。
つまり、対価が株式だと持株比率の分散は避けられません。
このように、対価に株式を用いた吸収合併では、存続会社既存株主の持株比率が下がってしまうという点に注意が必要です。
吸収合併の手順
吸収合併の手順は「契約の締結から登記、そして事後書類の備置まで」、いくつもの決まったステップを踏むことが必要です。
存続会社と消滅会社が協議して合併契約書を作成します。
契約内容には、本店の所在地や社名、株主への対価、効力発生日などを定めます。その後、両社の取締役会で承認を取り、契約を締結します。
合併契約は株主総会でも承認が必要です。
公開会社は開催の2週間前、非公開会社は1週間前までに招集通知を出さなければなりません。
官報に公告を出し、既知の債権者には個別に通知します。
債権者は反対意見を出すことができますが、その期間は最低でも1カ月設ける必要があります。
合併に反対する株主は、自分の株を会社に公正な価格で買い取るよう請求できます。
請求の期限は効力発生日の20日前までです。
合併契約書に定められた効力発生日に、合併が成立します。
曜日や祝日に関係なく、その日に効力が発生する点が特徴です。
効力発生日から2週間以内に法務局で登記をします。
存続会社の登記変更と、消滅会社の解散登記を同時に行わなければなりません。
合併後、効力発生日から遅滞なく事後開示書類を本店に備えます。
書類は6カ月間保存する義務があります。
以上のように、吸収合併は契約から登記、書類の備置まで一連の流れをきちんと踏むことが大切です。
もし不安がある場合は専門家に相談しながら進めると安心です。
吸収合併で準備すべき契約書・登記関連
吸収合併は、存続会社が消滅会社のすべての権利義務を引き継ぐ大きな手続きです。
そのため、法的に必要な契約書や登記関連書類をそろえ、適切に手続きすることが重要となります。
書類の不備や提出忘れがあると、合併そのものが無効となるリスクもあります。
吸収合併で必要となる契約書や登記関連書類は、以下です。
上記の書類は法務局や関連機関へ、法定期限までに提出する必要があります。
例えば、登記申請書や証明書類などは「合併効力発生日から2週間以内」が原則です。
吸収合併のスケジュールについて
吸収合併は、事前準備から効力発生・登記までおよそ2カ月前後かかるため、効力発生日から逆算して余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
特に債権者保護手続きや株主への通知には期間の制約があるため、ひとつでも手続きを忘れてしまうと全体の進捗に大きく影響が出る恐れがあります。
具体的な吸収合併のスケジュール例は、以下です。
| 時期 | 主な手続き |
|---|---|
| 1月中旬 | 合併の準備開始 |
| 2月上旬 | 取締役会で合併承認決議、官報公告の申込み |
| 2月中旬 | 合併契約の締結 |
| 2月下旬 | 債権者への催告・公告、合併契約書等の事前開示書類の備置 |
| 3月上旬 | 株主総会招集通知、反対株主への通知 |
| 3月下旬 | 株主総会の承認、債権者異議申述期間の満了 |
| 4月1日 | 合併の効力発生 |
| 4月1日以降 | 登記申請(効力発生から2週間以内)、合併に関する書類の事後備置 |
吸収合併で最も大切なのは、効力発生日を先に決めて逆算でスケジュールを組むことです。
法定手続きに漏れがあると大きなトラブルとなる可能性があるため、専門家のサポートを受けながらスケジュールを設定することをお勧めします。
吸収合併に関してよくある質問
吸収合併に関するよくある質問を紹介します。
- 吸収合併の事例にはどのようなものがありますか?
- 吸収合併後は社員の雇用契約や待遇はどのように扱われますか?
- 吸収合併に関する会計仕訳はどのように処理しますか?
- 吸収合併の事例にはどのようなものがありますか?
-
吸収合併の事例は、以下の通りです。
スクロールできます例えば、2021年には「三菱UFJリース」と「日立キャピタル」が合併し、リース業界で2位の規模となりました。
他にも、2017年の「JXエネルギー」と「東燃ゼネラル石油」の吸収合併によって、「ENEOS」が誕生し業界1位のシェアを実現しました。
食材宅配の分野でも、「オイシックス」と「らでぃっしゅぼーや」など複数社の吸収合併によってトップ企業となった事例があります。
- 吸収合併後は社員の雇用契約や待遇はどのように扱われますか?
-
吸収合併後も社員の雇用契約や待遇は基本的にそのまま引き継がれます。
日本の会社法により、消滅会社の雇用契約や就業規則が存続会社へ承継される仕組みがあるためです。
上記の仕組みにより、合併だけを理由に社員が解雇されたり、突然待遇が大きく悪化することはありません。
- 吸収合併に関する会計仕訳はどのように処理しますか?
-
吸収合併の会計仕訳は、被合併会社の資産や負債を時価評価で引き継ぎ、発行した新株や取得対価との差額を「のれん」などとして計上する方法が一般的です。
借方 金額 貸方 金額 摘要 現金・預金 1,000,000 借入金 1,000,000 引き継いだ負債 売掛金 2,000,000 資本金 2,500,000 発行新株 のれん 500,000 差額(発生時のみ計上) - 合併で受け取った資産や負債は借方・貸方に記録する
- 株式などで支払った合併対価は「資本金」として貸方に計上
- 取得対価が純資産時価より多い場合は「のれん」計上。少ない場合は「負ののれん」となり、仕訳方法が異なります
仕訳の処理には「資産・負債の時価評価」「のれん」や「負ののれん」計上がポイントであり、ケースごとの違いに注意しながら正しく記録することが大切です。
まとめ
吸収合併とは、一方の会社が他方を取り込み、権利義務や資産をすべて承継して事業を統合する仕組みです。
経営効率化やシナジー効果、市場シェア拡大などを狙いとして活用され、多くの企業で事業成長の手段となっています。
一方で、合併効力発生日にあわせたシステム・組織統合の難しさや、株主比率の低下、煩雑な手続きといったリスクもあるため、メリットとデメリットを正しく理解したうえで進めることが重要です。
吸収合併を検討している経営者・担当者の方は、まず効力発生日を軸としたスケジュール管理を徹底し、必要書類や手続きを漏れなく準備することが大切です。
必要に応じて専門家に相談しながら進めることで、トラブルを回避できます。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
吸収合併は、経営資源の統合や効率化を進める有効な手段である一方、複雑な法的手続きや株主・債権者対応、人材や組織の調整といった課題が伴います。
こうした局面では、専門的な知識と豊富な経験を持つ第三者の支援が欠かせません。
日本プロ経営者協会は、国内最大級のプロ経営者ネットワークを活かし、中小企業や医療機関など多様な組織の事業承継・経営統合を数多くサポートしてきました。
親族内承継からM&Aによる第三者承継まで幅広く対応し、承継後の経営体制の確立や成長戦略まで伴走型で支援します。
吸収合併や事業承継で不安を感じている経営者の皆さまは、ぜひ一度、日本プロ経営者協会にご相談ください。