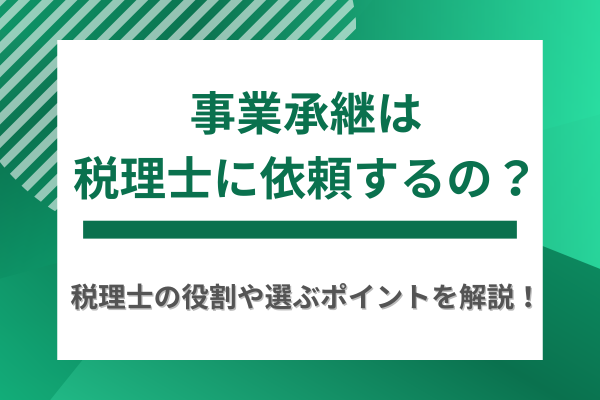「事業承継は税理士に依頼すべき?」
「税理士に相談するタイミングは?」
事業承継を行う際は、税理士に依頼することがおすすめです。
自社株の評価額算定、相続税・贈与税の節税対策、事業承継税制の活用など、複雑な手続きが多く、専門知識なしでは対応が困難なためです。
税理士への相談は、承継予定時期の5年前がベストタイミングとなります。
今回は、「事業承継で税理士に依頼するメリット」や「税理士選びのポイント」などについて詳しく解説していきます。
これから事業承継を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
監修者

代表理事
小野 俊法
経歴
慶應義塾大学 経済学部 卒業
一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。
その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。
その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。
投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。
事業承継とは
事業承継とは、会社の経営権や資産、経営理念などを次の世代の経営者に引き継ぐことです。
事業承継が必要な理由は、経営者の高齢化が進んでいるからです。
2023年時点で経営者の平均年齢は60歳と過去最高を更新しており、このまま何もしないと廃業が増加して貴重な雇用や技術が失われてしまう可能性があります。
また、後継者不足も深刻な問題となっています。日本政策金融公庫の調査によると、廃業予定企業のうち約3割が後継者難を理由に挙げています。
- 親族内承継:現経営者の子をはじめとした親族に承継する方法
- 従業員承継:社内の役員や従業員に承継する方法
- M&A(第三者承継):社外の第三者に承継する方法
事業承継は会社の未来を左右する重要なプロセスです。計画的に進めることで、技術やノウハウを次世代に残し、会社の持続的な成長を実現できます。
事業承継は税理士に依頼することがおすすめ
事業承継でお悩みの方は、税理士に依頼することをおすすめします。
事業承継は複雑な手続きが多数あり、素人だけでは対応が困難だからです。
- 自社株の評価額を正確に算出できる
- 相続税や贈与税などの節税対策が可能
- 事業承継税制などの特例制度も活用できる
税理士のサポートにより後継者の税負担をゼロにした小売業の会社があります。
この会社は事業承継税制を活用し、民法特例も適用することで、スムーズな承継を実現しました。
また、中小企業庁の調査によると、事業承継の相談相手として7割以上の企業が税理士を選んでいます。
事業承継について税理士に相談するタイミング
実際の承継予定時期の5年前には税理士に相談することをおすすめします。
事業承継では、会社の株式の価値を下げたり、相続税や贈与税を減らすための対策が必要だからです。
これらの対策は、決算をまたがないと効果が出ないものが多く、時間がかかります。
たとえば、役員退職金を支払って自社株の評価額を下げる方法では、決算によってその年の純資産や利益の額が確定してはじめて効果を得ることができます。
また、後継者の育成や株式譲渡の手続きにも長い時間が必要で、場合によっては数年単位の準備期間が必要になることもあります。
親族内承継の場合、後継者の育成や自社株の評価対策に時間がかかり、事前準備の期間は5年以上かかるケースも少なくありません。
事業承継までの期間が5年あれば、承継に向けた対策の選択肢が豊富にあり、余裕を持って対策することができます。
事業承継の実務を税理士に依頼する手順
事業承継の実務を税理士に依頼する手順は、以下です。
まず税理士事務所に連絡して、無料相談を申し込みます。この段階では、事業承継の基本的な流れや税務上の課題について説明を受けることができます。
税理士があなたのニーズを詳しく聞き取ります。
具体的には以下の内容を整理します。
- 承継方法(親族内承継、親族外承継、M&A)の希望
- 自社株の評価額の算定
- 相続税・贈与税対策の必要性
- 事業承継税制の可否
税理士から業務内容に応じた見積もりを提示してもらいます。
複数の税理士事務所から見積もりを取ることで、適正な価格を把握できます。
内容と費用に納得したら、契約書を取り交わします。契約書では対応範囲や費用について明確にしておくことが重要です。
事業承継を成功させるためには、税理士との連携が欠かせません。
段階的な準備を通じて、税務面でのリスクを最小限に抑えながら、スムーズな事業の引き継ぎを実現できます。
事業承継における税理士の役割

事業承継における税理士の役割は、主に3つあります。
- 税務に関するアドバイス
- 自社株や事業資産の評価・整理
- 資金調達・納税資金対策
税務に関するアドバイス
事業承継には相続税や贈与税などの複雑な税務問題が発生するため、専門知識を持つ税理士のサポートが不可欠になります。
税理士は承継方法やタイミングについて助言し、税金の負担を考慮した最適な提案をしてくれるのです。
税理士の主な作業内容として、まず自社株の評価額を算定し、贈与や相続などの承継方法を検討します。
さらに事業承継税制の申請書類作成や、納税資金の確保に関するアドバイスも行います。
親族外承継の場合は、後継者の資金調達支援や株式取得のための財務計画も提案してくれます。
自社株や事業資産の評価・整理
非上場企業の自社株は客観的な評価額が示されておらず、国税庁の「財産評価基本通達」に基づく複雑な計算が必要です。
また、相続税や贈与税の計算には正確な評価額が求められるため、専門知識を持つ税理士のサポートが欠かせません。
- 自社株の評価計算:類似業種比準価額方式、純資産価額方式、配当還元方式による評価
- 事業資産の整理:企業資産と個人資産の適切な分離と評価
- 税務対策の提案:評価額を適正に抑える方法の検討
- 承継計画の策定:最適な承継方法とタイミングの助言
税理士による自社株・事業資産の評価と整理により、円滑な事業承継と税負担の軽減が実現できます。
資金調達・納税資金対策
事業承継では、税理士が資金調達と納税資金対策の両面でサポートを行います。
事業承継では高額な相続税や贈与税が発生することが多く、後継者が資金不足に陥るリスクがあります。
相続税は相続発生後10ヶ月以内に現金で一括納付することが原則で、現金を期限までに準備しなければなりません。
このような複雑な問題に対して、税理士の専門知識が必要となります。
税理士が行う作業内容は以下の通りです。
| 作業項目 | 詳細 |
|---|---|
| 資金調達支援 | 金融機関からの融資や補助金活用をサポートする |
| 納税資金対策 | 生命保険や退職金を利用し、納税時の現金不足に備える提案を行う |
| 納税シミュレーション | 納税額の試算や資金計画の策定を行う |
| 資金繰り相談 | 納税に必要な現金確保の方法やスケジュールの調整を支援する |
上記の作業により、資金調達や納税資金対策で悩む経営者も安心して事業承継を進められるようになります。
事業承継に強い税理士を選ぶポイント
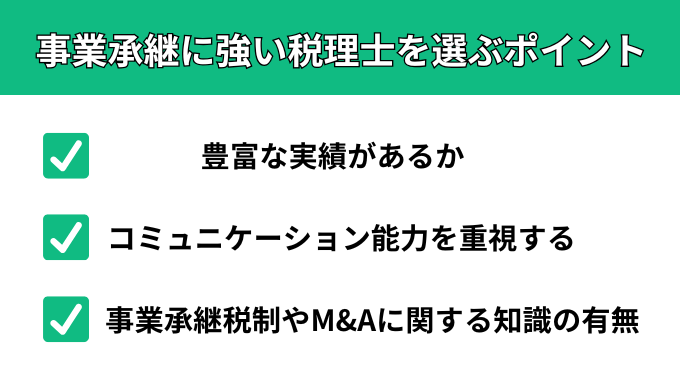
事業承継に強い税理士を選ぶ際に必ずチェックしておきたい「3つのポイント」をご紹介します。
- 豊富な実績があるか
- コミュニケーション能力を重視する
- 事業承継税制やM&Aに関する知識の有無
豊富な実績があるか
実績が豊富な税理士は、企業の規模や業種ごとの事情に対応できる柔軟性があり、想定外のトラブルにも対応できます。
事業承継のノウハウがあることは非常に重要なポイントで、実績が豊富な税理士ほど、状況に応じた最適な提案を受けられる可能性が高くなります。
- ホームページや公式資料で「事業承継対応実績」の件数や事例を探す
- 直接面談や電話で「これまで何件ほど事業承継をサポートしたか」「どの業種の事案を経験したか」などを質問する
- 支援した企業名や、取引先の業種・規模に関する具体的な事例を教えてもらう
- お客様の声や口コミ、成功事例などを掲載しているか確認する
- 希望する業種・規模に近い実績があるかを確認する
- 必要があれば、第三者機関や専門サービスの紹介ページ等から成約実績やサポート件数をチェックする
- 所属団体や専門資格(事業承継士など)の有無を確認する
実績数を必ず確認し、具体的な成功事例を聞いて判断しましょう。
コミュニケーション能力を重視する
事業承継に強い税理士を選ぶときは、コミュニケーション能力を重視することが大切です。
なぜなら、事業承継は短期間で完了するものではなく、長期にわたるやりとりが必要となるからです。
税理士との信頼関係が築けなければ、スムーズな進行が難しくなります。
また、現経営者と後継者候補、従業員、取引先など、多くの関係者との調整が必要となるため、税理士には高いコミュニケーション能力と調整力が求められます。
具体的には、経営者や後継者の意向をていねいにヒアリングしてくれるか、専門用語をわかりやすく説明してくれるか、不明点や悩みに対して迅速に回答してくれるかという点をチェックしましょう。
事業承継税制やM&Aに関する知識の有無
事業承継に強い税理士を選ぶには、事業承継税制やM&Aに関する専門知識があることが最も重要です。
なぜなら、事業承継税制は複雑な制度であり、一般措置と特例措置の違いや、納税猶予の要件を正しく理解していないと、適切な提案ができないからです。
また、M&Aは株式譲渡や事業譲渡など多様な手法があり、それぞれのメリット・デメリットを把握していることが求められます。
したがって、事業承継の実績が豊富で、税制やM&Aの最新知識を持つ税理士を選ぶことが重要です。
事業承継における税理士への報酬
事業承継における税理士への報酬は、100~500万円程度が一般的な相場となっています。
税理士の報酬は2002年に規定が廃止され、各税理士が自由に設定できるようになったことから、事務所によって料金体系が異なります。
業務別の報酬相場
| 業務内容 | 報酬相場 |
|---|---|
| 特例承継計画の策定・作成 | 10万円~80万円 |
| 相続税評価額の算出 | 10万円~60万円 |
| 事業承継税制の手続き | 50万円~250万円 |
| 株価算定 | 10万円~50万円 |
| 年次報告・継続届出 | 5万円~15万円 |
事業承継における税理士への報酬は、業務の複雑さや会社の規模に応じて変動しますが、総額で100~500万円程度を見込んでおくことが現実的です。
複数の税理士事務所に相談し、見積もりを比較検討するようにしましょう。
事業承継を税理士に依頼する際によくある質問
事業承継を税理士に依頼する際によくある質問をご紹介します。
- 事業承継を税理士に依頼するメリットは何ですか?
- 一般的な税理士と事業承継専門の税理士の違いは何ですか?
- 税理士に依頼してから事業承継完了までの期間は?
気になる点や知りたいポイントがある方は、ぜひご覧ください。
事業承継を税理士に依頼するメリットは何ですか?
税理士は税務のプロフェッショナルであり、事業承継税制や各種控除制度を活用した節税対策を提案してくれます。
事業承継を税理士に依頼するメリットは、以下です。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 税負担の軽減 | 事業承継税制や生前贈与を活用した効果的な節税対策 |
| 専門知識の活用 | 自社株評価や相続税対策などの複雑な税務処理 |
| 相談しやすさ | 顧問税理士なら会社の内情を把握しているため、スムーズに相談が可能 |
| 経営面のサポート | 事業承継後の経営体制についてもアドバイス |
事業承継を税理士に依頼することで、税務面でのサポートや専門知識を活用した効果的な対策が可能になります。
一般的な税理士と事業承継専門の税理士の違いは何ですか?
一般的な税理士は日常的な税務処理が中心ですが、事業承継専門の税理士は自社株評価や事業承継税制など、より専門的な知識を持っています。
| 項目 | 一般的な税理士 | 事業承継専門の税理士 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 日常的な税務処理・申告業務 | 事業承継に関する税務全般 |
| 知識の範囲 | 基本的な税法知識 | 自社株評価・事業承継税制・M&A税制 |
| 対応できる業務 | 確定申告・法人税申告など | 承継プラン策定・株式承継支援 |
| 経験・実績 | 一般的な税務案件 | 多数の事業承継案件 |
| 専門家との連携 | 限定的 | 弁護士・司法書士等との幅広いネットワーク |
事業承継には、通常の税務処理とは異なる専門的な知識が必要です。
自社株の評価額算定、相続税・贈与税の計算、事業承継税制の適用など、複雑な手続きが多く含まれます。
したがって、事業承継を考える際は、一般的な税理士よりも事業承継専門の税理士に相談することをおすすめします。
税理士に依頼してから事業承継完了までの期間は?
税理士に依頼してから事業承継が完了するまでの期間は、一般的に5年~10年程度かかります。
後継者の育成、自社株の評価対策、相続税や贈与税の節税対策など、複雑な手続きを段階的に進める必要があります。
特に親族内承継では、後継者の教育や株式譲渡のプロセス決定に多くの時間がかかることが要因となっています。
まとめ
事業承継を成功させるためには、税理士との連携が欠かせません。
税理士は自社株の評価額算定、相続税・贈与税の節税対策、事業承継税制の活用など、複雑な税務処理を専門的にサポートし、後継者の税負担を最小限に抑える役割を担います。
事業承継を検討している方は、できるだけ早い段階で税理士に相談し、複数の事務所から見積もりを取ってみてください。
自身のニーズや会社の状況に合った税理士を選ぶことが、後悔のない事業承継につながります。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
事業承継は税負担の軽減だけでなく、後継者の育成や経営体制の構築など、多面的な課題に取り組む必要があります。
適切な事業承継を実現するためには、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルのサポートが不可欠です。
一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。
JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。
経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。
事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。