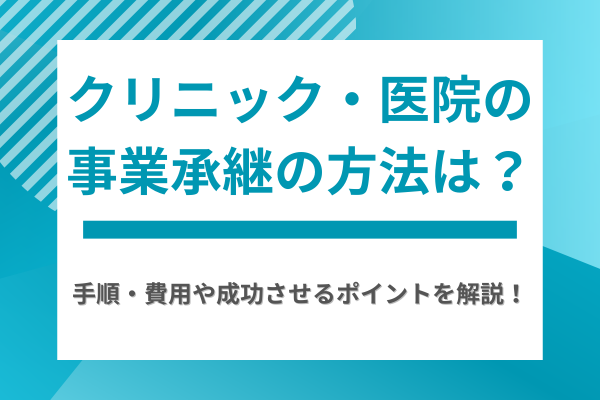「クリニック・医院を事業承継する方法は?」
「クリニック・医院の事業承継を成功させるポイントは?」
クリニック・医院の事業承継は親族内承継、従業員への承継(MBO)、第三者承継(M&A)の3つの方法があります。
現在、半数以上のクリニックが後継者不在のため、早期の対策が必要です。
- 早い段階から引き継ぎ計画を立てる
- 経営理念や診療方針をしっかりとすり合わせておく
- 資産状況・負債や医療機器の状態などを把握しておく
今回は、「クリニック・医院の具体的な承継方法」や「クリニック・医院の事業承継を成功させるポイント」などについて詳しく解説していきます。
事業承継を検討している医院経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
クリニック・医院における事業承継の現状
クリニックや医院の事業承継について、不安を感じている方が増えています。
院長の高齢化に対し、後を継ぐ人が見つからない状況が多くなっているためです。
親族へ引き継ぐ方法が以前は一般的でしたが、最近は親族が承継を望まなかったり、適任者がいなかったりすることがよくあります。
第三者への譲渡(M&A)が選ばれる例も増加していますが、費用、スタッフとの調整、引き継いだ後の経営に不安を抱える声が多いです。
実際に、2024年の調査ではクリニックや医院のうち半数以上が後継者不在のまま運営されています。
そのため、まずは早めに事業承継の準備を始め、専門家に相談することが重要です。
クリニック・医院を事業承継する方法

クリニック・医院を事業承継する方法は、以下の通りです。
- 親族内承継
- 従業員への承継(MBO)
- 第三者承継(M&A)
上記の承継方法について解説していきます。
親族内承継
親族内承継とは、クリニックや医院などの経営者が自分の子どもや配偶者、兄弟姉妹、孫などの親族に事業を引き継いでもらう方法を指します。
たとえば、親が運営するクリニックを子どもが後継する場合、まずは診療の方針や理念について話し合い、承継のタイミングを決めます。
その上で資産や負債、経営状況を一緒に確認し、税理士などの専門家にも相談しながら承継計画を立てます。
そして、行政手続きや名義変更を進めて承継を実行します。
親族内承継なら、お互いに経営上の考え方のすり合わせができるので、無理なくクリニックを次世代に残しやすいです。
また、贈与税・相続税の対策もしやすくなります。
従業員への承継(MBO)
クリニックや医院を従業員へ承継する「MBO(エムビーオー)」は、院の風土や理念を守りたい方におすすめです。
従業員への承継(MBO)とは、「マネジメント・バイアウト(Management Buy Out)」の略語で、今までクリニックや医院で管理をしてきた役員や従業員が、現在の経営者から事業や経営権を引き継ぐ方法です。
院長や経営者の家族以外で医院を理解しているスタッフが後継者となる場合に選ばれています。
働いている従業員が経営権を持つことで、院の理念や診療スタイルを守りやすくなり、スタッフや患者さんも安心しやすいメリットがあります。
一方で、MBOを進めるにはクリニックや医院の株式や事業そのものを、従業員が資金を集めて買い取る必要があるため、資金調達や専門家との手続きが欠かせません。
第三者承継(M&A)
クリニックの第三者承継(M&A)は、親族以外の医師や医療法人にクリニックを引き継ぐ方法です。
親族内に医師の資格をもつ後継者がいないクリニックが増えているためです。
従来の親族承継とは異なり、第三者承継では地域医療を維持しながら円満にリタイアできます。
医院を閉院せずに患者やスタッフを守れる点で、地域社会にとって価値の高い選択肢となっています。
また、譲渡金を受け取れるため、引退後の生活資金確保にも効果的です。
クリニック・医院の開設形態によって異なる事項
開設形態が「個人開設」か「医療法人」かで、譲渡・行政手続き・資金調達や税金など多くの項目で異なります。
開設形態ごとに、経営権の引き継ぎ方、必要な資金や税金まで異なるからです。
自分に合わない形態だと、負担や手間が増えてしまいます。
| 項目 | 個人開設クリニック | 医療法人クリニック |
|---|---|---|
| 譲渡方法 | 事業譲渡(個人から個人、または医療法人へ) | 出資持分譲渡+社員の入れ替え |
| 行政手続き | 廃止届・新規開設届など両者で多く必要 | 持分譲渡で許認可変更は不要な場合が多い |
| 資金調達 | 譲受人個人が融資や自己資金で対応 | 法人として金融機関から借り入れ |
| 税金 | 分離課税・総合課税 最大45% | 出資持分譲渡の場合約20.3% |
資金調達方法も開設形態により異なります。
個人開設では買手個人が譲渡対価を支払い、不足分は個人が金融機関から融資を受けます。
医療法人開設では出資持分と退職金の合計が対価となり、医療法人が借入れを行う場合があります。
形態ごとの特徴をきちんと理解して、自分にとって負担が少なく有利な方法を選ぶことが大切です。
クリニック・医院における事業承継の流れ
医院承継は一般的な事業承継とは異なり、医療法に基づく複雑な手続きが必要です。
また、地域医療への影響や患者への配慮も考慮しなければならないため、綿密な計画が求められます。
親族への承継の場合
前院長と後継者が医院の理念を共有し、承継のタイミングを話し合います。
医院承継に詳しい税理士や弁護士に相談します。
医院の財務状況や設備、患者数などを詳しく調査します。
地域のニーズに合わせて、承継後の運営方針を検討します。
具体的なスケジュールと手続きを計画します。
行政手続きを含む実際の承継を行います。
第三者への承継(M&A)の場合
医院M&Aに特化した仲介会社、税理士、弁護士に相談します。譲渡理由や希望条件を整理し、承継の可能性を検討します。この段階で、大まかなスケジュールと必要な準備について説明を受けます。
情報漏洩を防ぐための秘密保持契約と、仲介会社との業務委託契約を結びます。手数料や業務範囲、責任の所在を明確にします。
過去3年分の決算書、患者数推移、スタッフ情報、設備状況、賃貸借契約書、医療機器のリース契約書などを仲介会社に提出します。
専門家が提出資料をもとに医院の適正価格を算定し、譲受候補者向けの概要書(ノンネーム)を作成します。立地条件や診療科目、年間売上高などが記載されます。
候補者との面談を行い、条件が合えば基本合意書を締結します。譲渡価格、引継ぎ期間、雇用継続などの基本条件を確認します。
譲受側が医院の財務状況、法的問題、リスク要因を詳細に調査します。会計士や弁護士による専門的な監査が行われます。
最終条件を確定し、最終合意書を締結します。許認可・名義変更などの必要手続きを完了し、対価の支払いと事業の引き渡し(クロージング)を行います。
医院承継は複雑なプロセスですが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、スムーズな引き継ぎが可能になります。
早めに準備をすることが大切です。
クリニック・医院の事業承継にかかる費用
クリニック・医院の事業承継で譲渡側にかかる費用は、主に仲介会社やアドバイザリー会社への手数料が中心となります。
事業価値の算出や専門的な手続きが必要なため、一定の費用負担は避けられません。
| 費用項目 | 内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 着手金 | M&A業務委託契約時の初期費用 | 50万円~200万円 |
| 月額報酬 | 仲介期間中の月次費用 | 月10万円~50万円 |
| 成功報酬 | M&A成立時の報酬 | 譲渡価格の3~10% |
| 事業価値評価費用 | クリニックの適正価格算出 | 50万円~300万円 |
| 税務・法務費用 | 専門家への相談・手続き | 50万円~200万円 |
なお、仲介会社によっては着手金や月額報酬を取らず、成功報酬のみという料金体系もあります。事前の確認が大切です。
クリニックの事業承継では、譲渡側も一定の費用負担が必要ですが、専門家の料金体系を事前に比較検討することで費用を抑えることができます。
クリニック・医院の事業承継を成功させるポイント
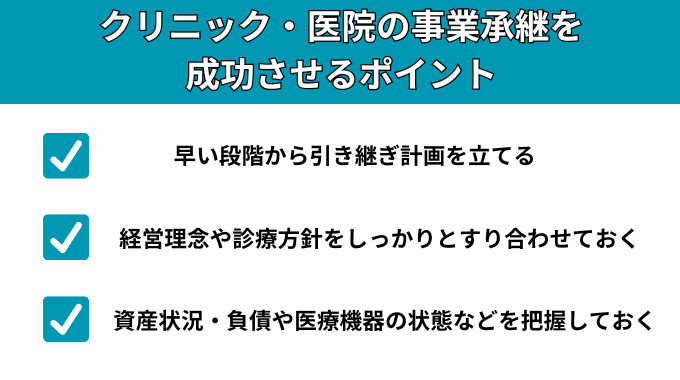
クリニック・医院の事業承継を成功させるコツは、主に3つあります。
- 早い段階から引き継ぎ計画を立てる
- 経営理念や診療方針をしっかりとすり合わせておく
- 資産状況・負債や医療機器の状態などを把握しておく
上記を押さえることで、患者さんの信頼やスタッフ体制を守りながら、スムーズで失敗の少ない承継が実現できます。
早い段階から引き継ぎ計画を立てる
クリニックの事業承継を成功させるために最も重要なのは、早い段階から引き継ぎ計画を立てることです。
クリニックの承継は複雑な手続きが多く、第三者承継では譲渡先候補の選定だけで最低半年から1年を要します。
親族内承継の場合でも、後継者の育成や経営に関する教育期間を確保するため、早い段階から準備を始める必要があります。
専門家は譲渡希望時期から逆算して2~3年前に準備を始めることを推奨しています。
経営理念や診療方針をしっかりとすり合わせておく
クリニック・医院の事業承継では、経営理念や診療方針をしっかりとすり合わせることが最も重要なポイントです。
これを怠ると、患者離れやスタッフの離職につながり、せっかくの承継が失敗に終わってしまいます。
専門家のサポートを受けながら、現状の資産や経営状況を把握したうえで、経営方針や診療科の方向性について話し合います。
どのような選択が地域医療に貢献でき、患者のニーズに応えられるかという視点も重要です。
そして「事業承継計画書」を作成し、今後の予測や具体的な数値目標なども含めた明確な承継計画を立てます。
資産状況・負債や医療機器の状態などを把握しておく
クリニックの事業承継を成功させるには、資産状況・負債や医療機器の状態を正確に把握しておくことが重要です。
情報を事前に整理することで、承継価格の適正な算定や承継後のトラブル防止につながります。
| 分類 | 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 資産状況 | 棚卸資産 | 医薬品・医療消耗品の在庫量と評価額 |
| 有形固定資産 | 建物・医療機器の時価評価と減価償却状況 | |
| 未収入金 | 未回収の診療報酬・患者支払い分 | |
| 負債状況 | 帳簿記載負債 | 借入金・未払金・リース債務 |
| 簿外債務 | 未計上の債務・契約上の義務・損害賠償責任 | |
| 医療機器 | 機器の状態 | 導入時期・修理履歴・老朽化の程度 |
| メンテナンス状況 | 定期点検記録・保守契約の有無 | |
| 買い替え計画 | 今後の更新予定・必要投資額 |
クリニックの事業承継においては、資産・負債・医療機器の状態を事前に把握することが大切です。
上記により適正な承継価格の算定が可能になり、承継後の予期せぬ費用発生を防げます。
特に高額な医療機器については、買い替え時期や修繕費用を含めた長期的な視点での評価が重要です。
クリニックの事業承継に関するよくある質問
最後に、クリニックの事業承継に関する疑問、よくある質問に回答します。
- クリニック・医院の事業承継で起こりやすいトラブルにはどのようなものがありますか?
- クリニック・医院の事業承継に失敗するケースには、どのような原因がありますか?
- クリニック・医院の事業承継に関する相談先はどこですか?
- クリニック・医院の事業承継で起こりやすいトラブルにはどのようなものがありますか?
-
クリニックの事業承継では、法的手続きから人間関係まで幅広いトラブルが発生しやすくなります。
トラブル分類 具体的な問題 影響 行政手続き 保険医療機関指定申請の遅れ 保険診療不可・資金繰り悪化 法的問題 事業報告書の未提出 役員変更拒否・承継遅延 人間関係 診療方針の相違 患者離れ・スタッフ離職 経営面 簿外債務の発覚 予想外の負担増加 契約関係 賃貸契約の引き継ぎ問題 建物使用トラブル 設備面 医療機器の所有権が不明 設備投資の重複 具体的なトラブル事例として、最も多いのは行政手続きの不備による診療開始の遅れです。
例えば、保険医療機関指定申請を忘れていると、承継から2~3か月間も保険診療ができず、資金繰りが急速に悪化してしまいます。
また、診療方針の違いから患者さんが離れてしまったり、必要な書類の提出漏れで役員変更が認められないといった問題も起こりがちです。
- クリニック・医院の事業承継に失敗するケースにはどのような原因がありますか?
-
クリニックの事業承継は患者離れ、スタッフ問題、経営・設備トラブルなどが原因で失敗するケースが多くあります。
原因 詳細 患者離れ 診療方針の変更により前院長時代の患者が他院に移る スタッフ問題 引き継いだスタッフとの人間関係や方針の相違による離職 経営状態の悪化 承継前から繁盛していない医院の継承による集患困難 設備・建物の老朽化 ランニングコストを考慮せずに初期費用の安さだけで判断 契約トラブル 賃貸借契約の名義変更拒否や行政手続きの不備 条件変更 売り手側による譲渡条件の大幅変更で交渉が破談 実際の失敗例としては、テナント賃借権の譲渡が不動産オーナーに拒否されて承継が白紙になったケースや、管理医師予定者が直前で辞退して案件が破談となったケースがあります。
また、医療法人の事業報告書提出漏れが原因で行政手続きが進まず、名称変更もできずに資材作り直しが必要となった事例もあります。
- クリニック・医院の事業承継に関する相談先はどこですか?
-
クリニックの事業承継で困ったときは、事業承継・引継ぎ支援センターや税理士、M&A仲介業者に相談するのが最適です。
相談先 特徴・メリット 事業承継・引継ぎ支援センター 全国にあり無料で相談可能。税理士や公認会計士が在籍 税理士・弁護士・公認会計士 税務や法務の専門知識でスムーズに手続きが可能 M&A仲介業者 第三者承継の交渉や手続きまで幅広くサポート 金融機関 財務面のアドバイスや資金調達の相談が可能 専門仲介会社 医療業界に特化したマッチングサービス クリニックの事業承継は、一般的な企業とくらべて法律的な手続きや許可の引き継ぎが複雑です。
そのため、専門知識を持った相談先でないと、適切なアドバイスをもらうことができません。
また、相談先によってはコストがかからず利用できるところもあり、クリニックの状況にあわせて選ぶことが重要です。
まとめ
クリニック・医院の事業承継は、院長の高齢化と後継者不足により多くの医療機関が直面する重要な課題です。
個人開設と医療法人では譲渡方法や税金負担が大きく異なるため、開設形態に応じた適切な選択が必要です。
承継には6か月から1年程度の期間を要し、仲介手数料や専門家費用として数百万円の費用がかかることも理解しておく必要があります。
今回紹介した承継方法や注意点を参考に、まずは現在のクリニックの状況を整理し、2~3年前から具体的な承継計画を立て始めましょう。
後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください
クリニック・医院の事業承継でお悩みの医師の皆様、後継者不足による将来の不安を感じておられませんか?
日本プロ経営者協会は、国内最大級のプロ経営者ネットワークを活用して、中小企業の事業承継課題解決に豊富な実績を持つ組織です。
医療業界の特殊性を深く理解した経験豊富なプロ経営者が、クリニック・医院の事業承継から経営統合まで、幅広いソリューションを提供いたします。
親族内承継から第三者承継(M&A)まで、あらゆる承継パターンに対応し、医療法に基づく複雑な手続きや行政対応、承継後の経営方針策定まで一貫してサポートいたします。
事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。